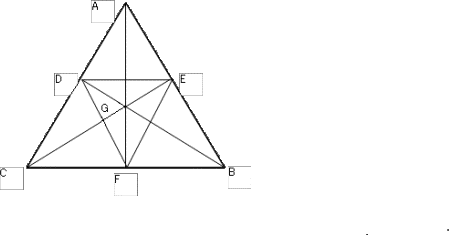
閑老人のつぶやき 思想について 3
今、渋谷要著『国家とマルチチュード 廣松哲学と主権の現象学』(社会評論社)を読んでいます。ネグリとハートが論じられているからというだけでなく、以前から廣松渉に興味を抱いていたためでもあります。このブント系とおぼしき新左翼の理論家は大変幅広く勉強していて、教えられることの多い書物です。
渋谷は第一部第二章「廣松渉の国家論と多元主義」で、ミシェル・フーコーの「権力のテクノロジー」を論じています。そしてフーコーの問題意識として次の言葉を引用しています。「ソ連をよく見てごらんなさい。そこの体制の下では、家族や、セクシュアリティや、工場や、学校に、権力関係は同じまま残っています。問題は、われわれが現在の体制のなかで、微視的なレベルで――学校、家族で――権力関係を変えることができるか、ということです」。また続いてフーコーの言葉を次のように紹介しています。
《フーコーは「資本主義システムはわれわれの生活にずっと深く浸透しています」として、資本主義は「人間の身体と時間とが労働時間と労働力に転化されるような、そして実際に余剰利潤になるべく使用されうるような、そのためのひとまとまりの技術」を必要としたという。
それこそ「人間の生存のレベルそのものに、微視的な、毛細管状の、政治的権力の網状組織が作り上げられ、それが人間を生産装置に固定して、彼らを生産のエージェントに、労働者にする必要があります」、「権力なしに余剰利潤はありません」と。
フーコーはこの剰余価値を生産する権力テクノロジーを「補助的権力」と規定する。「政治権力といわれているものではない」が、資本主義国家を社会的に形成している現場の権力が「補助的権力」といわれるものだ。》(以上、引用箇所省略)
上の指摘を参考にして、組織の運営のどこに問題があるかを考えてみたいと思います。
ここでは経営学の世界でよく知られた「七つのS」について触れてみます。例のTH図を参考にして、七つのSを次のように配置してみました。(下図参照、なおTH図については「哲学の区分」の項で既に取り上げました。)
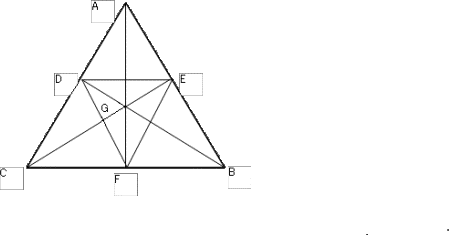
A=シェアリング、B=ストラクチャリング、C=スタッフィング、D=スキル、E=スタイル、F=システム、G=ストラテジーとなります。この構造を理解するために、「七つの疑問詞」をやはりTH図に当てはめ、両者を関連させてみると便利です。
その場合には、A=why、B=what、C=who、D=how、E=which、F=where、G=whenとなります。(いわゆる5W1Hにはwhichが欠けています。)
A 組織の構成員全体にシェアされるべきものは、その組織が生産する(物質的、非物質的)プロダクトの価値、あるいは「ねうち・ねだん・ねらい」に関わっています。そこに組織の使命があります。why―becauseのbecauseはby cause thatのことですが、そのコーズ(大義)を共有することがシェアリングの基本であると言えます。しかし往々にしてそのコーズが組織全体で共有されることが困難であるのは、組織には規模に応じた階層構造があり、また組織の内部に派遣社員や業務請負企業が入り込んでいるからです。トップダウンであてがわれたコーズは、朝礼のときに復唱される経営理念・社是のように、形骸化する傾向があります。シェアリングにも権力関係から来る傾き(強制)があります。
B 何か(what)あるものには、そのものの構造があります。文には文の構造(センテンス・ストラクチャー、文法)があり、分子には分子構造があります。組織にも組織構造があります。組織構造(組織図)は権力関係の図式化と言うべきものです。組織のピラミッドの上に行くほど、権力が増大します。権限が増し加わることは、説明責任の増大をも意味することです。しかし今日目立っているのは、組織の位階の上位を占める者たちの言い逃れや誤魔化しです。往々にして下位のものが責任を取らされます。
C スタッフィングとは組織構造の中で誰(who)がどの部署につくかの問題です。サラリーマンはこのことで一喜一憂します。スタッフィングを決めるのは役員であって、下から選挙によって決められることはほとんどありません。しかし最近は役職について重たい責任を引き受けることを嫌がる社員が増えていると聞きます。それを最近の若者の心理的傾向として説明することもできるでしょうが、リストラなどで会社への忠誠心が揺らいでいる証左であるとも受け取れます。
D 組織内の個々の部署、職位には、そこで求められる固有のスキルがあります。スキル(技能)とはhow to doの問題です。スキルに共通して求められるのは「のうりょく・のうき(納期)・のうりつ」です。ここでの能力とは特定の仕事を期間内に効率よく(能率的に)仕上げることができるという意味です。現代人の忙しさの理由の大半はここにあります。その意味で組織内では人間の労働力が道具化されています。役割を遂行するとは、特定のスキルを行使するということであって、そこに大なり小なり習熟(熟練)の問題があります。習熟とは動きに無駄がないということを意味しています。
E スタイルはどちら(which)を選ぶかによって決まります。「である」調にするか、「です・ます」調にするかで、文章のスタイル(文体)が決まります。「派手」にするか、「地味」にするか、あるいはカジュアルにするか、フォーマルにするかで、服装のスタイルが決まります。組織にも組織のスタイルがあります。社風・校風などはこの組織のスタイルの問題です。組織のスタイルはトップの選択によって決まりますが、社員間の相乗作用の問題でもあります。いわゆる伝統がそこに働いています。
F システムとはwhere to put in orderの問題です。串刺しされた焼き鳥は具材の種類と串に刺される順番が決まっています。システムの原始的な形態であると言えます。組織の中にも様々なシステムがあって、それによって組織が円滑に機能します。物のおき場所や出し入れの仕方、仕事の流れや手順など、システムは随所にあります。組織の基底を支えているのがシステムです。今日ではコンピュータによってシステムが管理されています。
G シェアリングが組織の根本原理に関わるとしたら、ストラテジーは組織の中心原理です。ストラテジー(戦略)は総合計画です。個々の部門の計画は、組織全体として総合される必要があります。あるいは組織全体の目標があって、個々の部門はそれに従ってそれぞれの計画を立てなくてはなりません。パート法に端的に示されているように、組織の計画はいつそれを実施するか(when to do)の問題です。また戦略はタイミングの問題です。どんなに優れた計画もタイミングを失すれば無効になります。
戦略は成功することもあれば失敗することもあります。それが失敗したとき、あるいは予想した条件が整わないときの代替案を用意しておくことも重要です。それは危機管理の一部です。でたとこ勝負で、戦略的でない組織は、運任せの組織運営をしていることになります。もしかしたら日本ではまだ戦略的な組織運営が定着していないのではないかと、私は考えています。あまりにも無責任な問題が多発しているからです。しかしそこには資本主義社会の行き詰まりという、もっと根本的な問題があるのかもしれません。
組織の役員会が戦略あるいは事業計画を最終的に承認し、それを執行する権限を最高執行責任者(CEO)に委ねます。そこに組織の権力の所在が示されています。それはフーコーが言うように、政治権力ではなく、補助的権力です。しかし両者の密接な関係のうちに今日の社会の根本問題が潜んでいるように思われます。
「メソドロジーの三角形」は今田高俊著『自己組織性―社会理論の復活―』(創文社、1986年)に出て来る言葉です。今田はその本のp.133で〈方法モデル5 メソドロジーの回転と変換理性〉を図示しています。その図は前項でも取り上げた「TH図」とよく似ています。その図を作成するのは煩瑣ですので、以下に言葉で説明します。
先ず大きな三角形を描きます。その三つの頂点は了解(上)、反証(右)、検証(左)を示します。次にその中に小さな三角形を描きます。その三つの頂点は意味(上)、仮説(右)、観察(左)を示しています。このとき大きな三角形は存在平面を、小さな三角形は認識平面を表わします。そして了解(大の上角)と意味(小の上角)をつなぐ線は解釈、反証(大の右角)と仮説(小の右角)をつなぐ線は演繹、検証(大の左角)と観察(小の左角)をつなぐ線は帰納を示すものとします。ただしこの大小の三角形はそれぞれ回転します(!)。すなわちこれによって「認識平面と存在平面の三角形を回転させる自由で柔軟な変換理性の構造」が図示されています。
これに私なりに手を加えて(やや単純化して)TH図で示すとすれば以下のようになります。すなわちA 解釈、B 演繹、C 帰納、D 観察、E 仮説、F 検証、G 着想となります。この図は回転しませんが、TH図の特徴として相互に自由に行き来することができます。今田の反証が抜けていますが、それは検証に含まれるものとします(検証可能性とは、裏返せば反証可能性のことです)。また今田の図では両三角形の中心(回転軸)は何も意味していません。しかし私はそこに着想をあてがいました。発想でもよいと思います。C.S.パースのabduction(通例の意味は誘拐、筋肉の外転)には適切な訳語がありません。仮に着想としておきます。なおTH図では存在平面と認識平面の区別がありません。それは図解の不備と言うよりは、私はそのように区別すること自体に余り意味を認めていません。
さてメソドロジーがそのようなものであるとしても、そこにどんな意義があると言えるでしょうか。その意義は、前項でも行ったような「重ね合わせ」(先の場合には七つのSと七つの疑問詞との重ね合わせ)によって、多少なりと理解可能なものになると思われます。そこでこのメソドロジーの三角形と「哲学の七つのターム」とを重ね合わせてみます。その場合には、解釈(定位)、演繹(規定)、帰納(限定)、観察(還元)、仮説(構成)、検証(措定)、着想(止揚)となります。
解釈(定位) 英語では理解することをunder-standと言います。またディルタイの言う感情移入も自己定位に関わります。解釈とは自分の身をどこに置くかの問題です。
演繹(規定) 演繹とは理論的にレギュレートされるということです。理屈の上では必ずそうなるはずだということが演繹(規定)の意味するところです。
帰納(限定) 人は共通する事実や出来事を無限に列挙することはできません。しかし実践的に限定された範囲内であっても、そこから一般的な結論を導き出します。
観察(還元) 観察とは、同時に観察される事物の認識主観への還元を意味しています。同じ事象を「観察」していても、専門家と非専門家との間では雲泥の差があります。そこに学習における習熟の問題があります。なお観察には実験も含まれます。
仮説(構成) これは文字通り理論を「組み立てる」(construct)ことです。この場合にはconstituteとconstructとはほとんど同じ意味で用いられます。
検証(措定) 検証は何かをposit(措定)する働きの一部です。すなわち〈Aがある〉、〈SはPである〉という思考の働きの一部として(あるいはその展開として)、検証と反証とがあります。
着想(止揚) 思考に行き詰まったとき、ふとそれを打開するアイデアが生まれてきます。それは現在自分がぶつかっている問題の解決が、思いがけないところにころがっているということの発見です。横超ということばがありますが、横っ飛びに別の領域からアイデアを盗み取ってくるような心の働きがアブダクションだと言えるでしょう。それを敢えて止揚(揚棄)と結びつけることによって、人間の観念の発展を見ることが可能になります。メソドロジーの中心に私はこの着想(止揚)を置きたいと思います。
メソドロジーをこのように理解すれば、そしてその限りでは、そこに「学問的」と「日常的」との区別はありません。母国語であれば誰でも文法に即して話をしています。しかし文法を文法として教えられると多くの人が苦手意識を持ちます。メソドロジーもそのようなものではないかと思われます。科学者も科学の方法について一々意識しているわけではありません。それを敢えて意識化すると、メソドロジーの三角形になるのではないかというのが、年来の私の持論です。
Cassell’s English Dictionary によるとhylomorphismとは、The philosophy that finds the first cause of the universe in matter. であると書かれています。「宇宙の第一原因を物質に見る哲学」がヒロ・モルフィズムであるとされています。ヒロ・モルフィズムとは唯物論のことであるということになります。しかしこの言葉はアリストテレスの哲学を言い表すものとしては「質料形相論」と訳されてきました。世界(実体)はヒュレー(質料、材料)とモルフェー/エイドス(形相、形態)とからできているという思想のことです。
内田弘はその著『三木清』(御茶の水書房、2004年)において、アリストテレスの四原因論に基づいてマルクスのMaterialismusの立場を説明しています。「アリストテレスは存在するものにはその根拠、すなわち原因が四つあると考えました。その四原因とは、形相因(エイドス、causa formalis)、目的因(テロス、causa finalis)、作用因(アルケー、causa efficiens)、質料因(ヒュレー、causa materialis)です」と言い、彫刻作品を例に挙げて、「彫刻家が形相因、大理石が質料因、彫刻家の精神が目的因、彼の肉体が作用因です」とした上で、次のように書きます。「若いときからアリストテレスを精読し、古代哲学者のなかでアリストテレスを最も好んだマルクスは、…精神は肉体に対して活動の形態を決定し指揮する要因であるから形相因であり、肉体は精神に形態を決定されるから質料因であるとみました」、「マルクスは博士論文のあと経済学を学んで書いた『経済学・哲学草稿』で、近代経済の世界における知識人と大衆の関係(人間の形相因と質料因との社会的分離)を資本家と賃金労働者との関係に洞察して、哲学批判は経済学批判にすすまなければならないことを確認しました」、「…マルクスは質料因(materia)が形相因(forma)よりも、存在論的に根源的である(materialiistisch)である、と観ます。この観点は拡大されて、目的因(=人間の精神・形相因)より作用因(=人間の肉体・質料因)、理論(=形相因)より実践(=質料因)がより根源的という観点になります。この観方をマルクスはMaterial-ismusといったわけですから、マルクスのMaterialismusは『質料因根源論』と訳すべき観点です。マルクスのマテリアリスムスは物象化論ではありません。むしろ逆であって、それは、社会的形相因(資本主義的価値関係)が社会的質料因(商品の他人にとっての使用価値)に体化する物象化を批判=解体する観点です」(以上、p.226~228、「第六章 唯物論と宗教観」からの引用)。
ここには「アリストテリコ・マルクシズム(アリストテレス的マルクス主義)」とでも言うべき立場が表明されています。それはアリストテレスの研究書を二冊出した三木清の思想ともつながってきます。内田は、また、三木の言う「自由な個性者が構想力の使用によって形成する創造的社会」というヴィジョンは、マルクスが資本主義のあとに展望した「自由な個性者」の社会(『経済学批判要綱』)と大きく重なるとも述べています。
このアリストテリコ・マルクシズムをヒロ・モルフィズムと言ってよければ、この立場を画期的に前進させたものは、物象化論の主唱者、廣松渉の「四肢構造論」ではないかと思います。廣松の「現相的所与―意味的所識」、「能知的誰某―能識的或者」という四肢的構成態は、対象的質料面(現相的所与)―対象的形相面(意味的所識)、主体的質料面(能知的誰某)―主体的形相面(能識的或者)と言い換えることが可能だと思われるからです。またその廣松の立場は、マイケル・ポラニーの暗黙知(質料的知、対象的質料面)と分節知(形相的知、対象的形相面)、人称的知識(「個人的知識」と訳されています)、すなわち主体的形相面(および主体的質料面=前人称的知の主体)と、相互的に補完されるべきものではないかと考えられます。いずれにしても、マルクスの「唯物論」は「タダモノ論」ではありません。またその認識論的対応物としての「反映論」とも無縁です。
(廣松の四肢構造論については、渋谷要『国家とマルチチュード 廣松哲学と主権の現象学』社会評論社、2006年、p.84~90、〔注解〕廣松の四肢構造論と「われわれとしてのわれ」の機制 参照。)
資本は雇用を創出します。しかし雇用関係を解除する(解雇する)のも資本です。企業という組織の一員となり、賃金を支給されなければ生きていけない労働者にとって、不況は最大の脅威です。人を活かす組織、自己実現の場であったはずの組織が、解雇によって、ある日突然自分にとって疎遠なものとなります。組織の中で生き抜いて行くためには、自分が組織に貢献する人間であることを実証しなければなりません。組織の存続と発展が至上目的であって、個々の労働者は取替えの利く歯車に過ぎません。経営環境が悪化すれば、労働条件も厳しくなります。労働者に雇用の機会を提供する資本は、同時に労働者を選別し、整理し、労働争議が起これば、排除することも辞しません(ロックアウト)。
当然のことですが、組織は人を必要とします。しかし組織の目的に貢献しない人間は排除されます。利潤を上げることが目的である企業組織においては、その目的によって人間が雇用され、また解雇されます。たしかに賃労働者は資本の奴隷であって、労働者の権利を守るはずの法律も、資本主義社会が危機的な状況に遭遇することによって、次第に資本家に都合がいいように改変されつつあります。権利は資本家に、義務は労働者にあるという関係は、貨幣によって生存の権利が保障される資本主義社会の、ある意味では当然の帰結です。お金がなければ無権利状態に置かれます。そしてお金を獲得するために、都市生活者はどこかの会社あるいは組織に就職して働かなければなりません。
企業が労働者を必要としているにも拘わらず、その企業が労働者の労働条件を悪化させ、賃金をできるだけ低く抑えようとする、というマイナスのスパイラル(負の螺旋運動)は不況下の特徴です。このとき企業は労働者に対して敵対的な相貌を帯びてきます。人を活かすはずであった組織は、単に労働者を搾取するだけの存在であったことが明らかになります。好況時のスローガンは、不況時には、それが単に美辞麗句であったことが暴露されます。企業は自己実現の場であるどころか、かえって自己喪失の場であることが、事実として示されてきます。その極端な例が過労死です。
組織が人を必要とするということは、組織には「3つのR」が求められるということを意味しています。リクルートメント(募集)、リテンション(維持)、レコグニション(顕彰)のことです。人を採用すること、採用された人たちを維持管理すること、その働きを認め褒賞を与えることは、人事管理の基本です。しかしもし人を採用しても、リテンションにおいて、労働者に責任だけがあって権利がなく、ろくな訓練も行なわれず、評価もされない(マイナスの評価しかされない)職場であれば、人を繋ぎとめておくことはできません。またレコグニションがなければ、人は働く意欲を喪失します。人は自分の働きが社会的に認知される(レコグナイズされる)ことによって生き甲斐を与えられます。褒賞の額が問題ではありません。しかし初めから人をこき使うことしか念頭にない職場であれば、そのような会社にはよほど困っている人しか残らないでしょう。
今日の企業組織にはリクルートメントだけがあって、他の二つのRを顧みる余裕さえなくなっているのだとすれば、それが長続きするとは到底考えられません。それこそ労働者を暴力的に会社に囲い込んでおく手段しか残されていないということになるからです。関西には実際に暴力団によって労務管理が行なわれていた業界がありました。
資本主義社会を存続させるために、国家という暴力団が労働者(国民)を管理するという構図だけは、どうか願い下げにしてほしいと思います。しかし私の眼前にちらついているのは、そのような悪夢です。国民の大半が「見た目」(イメージ)だけで政治家を選び、ひたすら景気が良くなることだけを望んでいる限り、不況と共にファシズムの影が忍び寄ってきます。国民の暴動や反乱を恐れる為政者は、その目を外の敵に向かわせようとします。またナショナリズムの神話を持ち出して、国民の意識を統一しようとします。今日の日本国民は(またしても)その罠にまんまと嵌りつつあるように思われます。
その昔、オールダス・ハクスレーの『ハクスレーの集中講義(人間の状況)』(片桐ユズル訳、人文書院、1983年)という本を読んだことがあります。この本は、1959年にハクスレーがカリフォルニア大学サンタバーバラ校で行なった16の連続講演をまとめたものです。晩年のハクスレーが自分のあらゆる知識を傾けて(その博識には舌を巻きます!)、環境問題、人口問題、戦争と国家の問題、あるいは宗教や、教育や、芸術の問題などを論じたもので、私はこの本によって、たとえば環境破壊が既に古代世界から始まっているのだということを強烈に印象づけられたことを記憶しています。
ハクスレーは、そこに自分の最後の希望を託すかのように、「人間の潜在的可能性」を論じることによって連続講演を閉じます。その講演でハクスレーは先ず人間の欲求について取り上げます。なぜなら「欲求との関係においてのみ潜在力を論じることができるからです」。人間には先ず基本的生物的欲求があります。食べ物への欲求、風雨や天敵・人敵から生命を守る欲求です。これらの欲求は「とにかく人が生存するためには満たされなくてはならないもの」です。次に、その一段上には、愛を与えることと愛を受けたいという欲求があります。この欲求が乳幼児期に満足させられないと、精神病者とか、ひどければ道徳的破産者になりやすいと指摘されています。愛の欲求と密接に関連したものに所属への欲求、アドラーが言うゲマインシャフトゲフュール(他人との共同体的感情)を満足させたいという欲求がります。それから、他人から尊敬され認められたいという強い欲求があり、もっと洗練されたものとして自尊心への欲求があります。次に来るのは、もっと洗練された欲求ですが、ある種の人々が環境に恵まれた場合にはとても強い欲求として抱かれるものです。いくつかのものが挙げられています。すなわち好奇心を満たしたい欲求、知識への飢えを満たしたい欲求、人生の秩序と意味への欲求、そして表現への欲求です。最後に来るのは、我々の能力の限界まで成長したい、我々の潜在力を実現したいという欲求で、これもまた、恵まれた環境においては基本的な欲求です。ハクスレーはマラルメの「永遠が彼を彼自身に変えるごとく」という詩の一節を引用しています。
ハクスレーは、これらの一連の欲求のリストからわかることとして、欲求が一種の階層をなして並んでいること、そして低次の欲求が満たされないときは、他の欲求は感じられることもないということを指摘しています。腹の減った人は、ただ一つの考えだけで頭が一杯です。つまり食べることしか考えません。また愛情と所属と尊敬と自尊心の欲求が満たされない限り、人間に固有の諸欲求――知識、秩序と意味、表現と成長への欲求は、感じることさえ非常に困難であり、ましてや、それらを実生活において実現し満足させることは、なおさら困難になると言います。ハクスレーは、A・H・マズロウの有名な学説を下敷きにして、これを述べています。(マズロウの説を「欲求五段階説」として整理すれば、①生理的欲求、②安全への欲求、③帰属(所属)への欲求、④自尊への欲求、⑤自己実現の欲求となります。)そして、マズロウの考えは大変役に立つとした上で、マズロウが高次の欲求(人間としての基本的欲求)を「弱い本能」だと考えることを支持します。それらは低次の生物的心理的欲求が満たされて初めて現われてくるものです。
これに付け加えて、人間の低次の欲求は強いけれども「一時的」である、高次の欲求は弱いけれども「永続的」である、と言うことができます。人間としての基本的な欲求は、一度目覚めれば、長続きするからです。それに対して、空腹などの生理的欲求は、それが一旦満たされると、暫くその欲求は消えてなくなってしまいます。
このような欲求の階層性という考えは、現代の心理学者が初めて発見したことではありません。たとえば仏教には十界という思想があります。広辞苑によれば、十界とは、迷・悟の階級を10種に分けたもので、地獄界・餓鬼界・畜生界・修羅界・人間界・天上界(以上迷界)と声聞界・縁覚界・菩薩界・仏界(以上悟界)のことです。天上界までの六界は迷妄の境界(凡夫の迷いの世界)でこれを六凡と称し、声聞界(しょうもんかい)からは証悟の世界(聖者の悟りの世界)でこれを四聖(ししょう)と言います。十界は十法界とも言います。仏教には、現代の科学的知見にも通じる、人間性に対する深い洞察があると言うべきでしょう。
人が生きていくために必要な基礎的訓練として、私は三つのものを上げたいと思います。すなわち、感覚訓練(sensible training)、統覚訓練(apperceptive training)、表出訓練(expressive training)のことです。しかしその一番手前にあるものは、おそらく禅などで言う調心・調息・調身でしょう。これらについて前出の『ハクスレーの集中講義』の最終章「人間の潜在的可能性」から適宜引用しつつ論じてみたいと思います。というのもハクスレーはそれらのうちに人間の潜在的可能性を見ようとしているからです。
「心を調え、息を調え、身体(からだ)を調える」というとき、第一に来るのは身体を調えること、あるいは姿勢を正すことです。その大切さについてハクスレーが述べていることは次のとおりです。
〈もうひとつの気づきのテクニークに触れて見たいとおもいます。それにはジョン・デューイがたいへん興味を持ちました。それはF・M・アレグザンダー(八十歳で死にましたが)によって、正しい姿勢に気づくようになるためのテクニークとして開発されたものです――特に首と胴体との正しい関係――これによって心身統一体は最善の状態で機能することが可能になります。デューイは、アレグザンダーのもとでこのテクニークを研究し、アレグザンダーの三冊の著書に序文を書きました。そのうちのひとつでデューイはとてもはっきりと、このテクニークが教育に対して持つ関係は、教育が人生全般に対して持つのと同じ関係である、そして、教育に対してほんとうに役にたつ可能性をあたえるものは、まさにこのテクニークだ、といっています。しかしデューイにしたがった何千何百の教育家のうち、わたしが知るかぎり実際にはだれひとりとして、この心身教育の方法に注意をはらわなかったのです。ところが心身教育の方法をデューイは、教育における最大重要事だとかんがえていたのです。それはただ見落とされ、わたしの知るかぎりでは、合衆国の学校でその方法を子どもの教育に応用しているところはただひとつしかありません。このことは、第一級の哲学者によって、はかりしれない実践的理論的意義をみとめられた重要な考えが、またしても、たまたま当時の学界の流行とあわなかったために、忘れられるがままにされていったという、もうひとつの例であります。〉
この前の段落でハクスレーは神経症を治癒するための方法について、パールズ、ヘファーリン、グッドマン共著『ゲシュタルト・セラピー』と、スイスの心理療法家ロジャー・ヴィトズ博士の治療法を取り上げ、基本的知覚的気づき能力の徹底的な訓練、あるいは一見もっとも些細なことに気づく訓練が、治療に効果的であるばかりでなく、心身の他の機能を行使するのにやっておかなくてはならないことであると指摘しています。そして次のように述べます。〈きわめて興味ぶかいことは、ヴィトズもゲシュタルト・セラピストも、実際には千年ニ千年前におこなわれていた東洋の哲学や心理学のいろいろな体系を復活させていることです。内部と外部のあらゆることを明晰に自覚していることが、仏教、密教、禅の心理学における標準的手続きでした。〉そして、偉大なるシバ神とその妻パルバティとの対話からなるテキストには、気づくことの練習118のリストが与えられているが、意識の訓練においてこれほど包括的なものは他になく、それにたいへんな価値のあることがやがて証明されるであろうと述べています。
ハクスレーは知覚について言います。〈わたしたちは一般化して次のようにいうことができると思います、わたしたちの知覚が鋭く精密で識別力があればあるほど、全体的にわたしたちの知能も高いのであると。これにはたいていのひとの同意が得られるとおもいます。たしかに、ある種の知能、たとえば論理的分析に必要な知能は、特に知覚機能が発達していなくても、たぶん存在し得ます。しかし同時にまたかんがえられることは、生活の状況とか精神活動に必要な知能は、論理的分析に要するほど特殊化され専門化されたものではない、ということです。これらの知能のためには、高度に発達した知覚能力がほんとうに必要なのです。わたしたちが学ばねばならないことは、わたしたちが今いるところで自分自身であることはどんな感じがするものか気づくことです。何がわたしたちをとりかこんでいるか知らねばなりません。まわりをとりかこんでいるものに対してわたしたちはどんなふうに反応しているか知らねばなりません。わたしたちの体のなかで何がおこりつつあるかを知らなくてはなりません。また自分たちが考えたり感じたり欲求したり意志したりしていることは何なのかについて、はっきりした認識をもたねばなりません。いいかえれば、わたしたちは例のソクラテスの格言にしたがわなくてはならない――それはじつはソクラテスの時にすでに言いふるされた格言だったのですが、「汝自身を知れ」ということです。〉ハクスレーは知覚の訓練を「感覚訓練」と「統覚訓練」とに分けては考えていません。しかしここに「はっきりした認識をもたねばなりません」と書かれていることが、私の言う「統覚訓練」にあたります。また「感覚訓練」には知覚、感情、想像力などが含まれます。すなわちセンシビリティには狭義の「神経による感覚力」だけでなく、気づき、感性、知覚、敏感さ、感受性なども含まれるものとします。そしてそれらがはっきり認識されている状態がアパセプション(統覚)と言われます。しかし感覚と統覚とはどこまでも相対的な区別にすぎません。
ハクスレーはまた次のように言います。〈まったく疑いもなく、訓練された知覚をもつひとにとって、この世界は、知覚の訓練されていないひとよりも、ずっと面白いのです。ですから、前者のようなひとは、西部劇とか殺人物語とかによる代用刺激や、または民族的反感とか国家主義的大さわぎによって生じるもっと危険な興奮をあまり必要としないのです。もしすべてのひとが、ふたたびブレークの文句にしたがって、知覚の扉が拭われてあれば、すべてのものはあるがままに、永遠の相のもとに見えます。そしてわたしたちすべての知覚の扉が拭われてあり、私たちが世界を永遠で聖なるものと見る習慣がついていたならば、闘牛へ行ったり、少数民族を迫害したり、外国人に対して敵意をもやしたりする必要がずっと減ることはあきらかです。というわけで、これらのことがたがいに助け合って作用します。おそかれ早かれわたしたちはなんらかの方法を発見し、それによって、アウェアネスとこれら各種の良い感情のトレーニングを組み合わせて、人間らしさの良い部分をふやし、わたしたちの多くの潜在的可能性を実現できるような日がくることを希望いたしましょう。〉
なお「表出訓練」に関連するハクスレーの言葉は以下の通りです。〈どうやらとてもはっきりしてきたことは、自覚ということをどのように発達させるにせよ、それは言語と意味についての認識とともに発達させなけれればならないということです。もし直接経験について自覚していこうとすれば、わたしたちは同時にまた、直接経験と、それから、わたしたちがその中に住んでいる記号とか言語とか概念の世界という、ふたつの世界のあいだの関係について自覚していなければなりません。わたしたちは氷山のようなものです。わたしたちは直接的現実の中に浮かんでいますが、直接経験から概念の世界に上ってくるに際しては、主義主張の風の中に突出してくることになります。というのは絶対的な直接体験というようなものはありませんから、わたしたちの経験はすべて、ことばによっていわば染められていることは確かです。ということはまた、ふつうわたしたちが行くよりもずっと深く直接経験の方向へ進むこともまた可能だということも疑いありません。というわけで、わたしたちに直接的にあたえられる経験と、それを考えたり表わしたり説明したりするためのことば、というこれらふたつのあいだの関係について自覚的になることはきわめてたいせつなことです。いいかえれば、二十世紀における言語学一般と意味論の発達は、あらゆるレベルでの教育に応用されるべきです。わたしの考えでは、トレーニングは知覚と想像力におけると同時に、言語の使用についても行なわれるべきです。これらはすべて本質的におなじことだとおもいます。〉ハクスレーはこの段落では特に言及していませんが、「表出訓練」には、文学・美術・音楽・演劇などの芸術の領域も含まれます。直ぐ前の段落で、想像力の訓練の必要性を説き、ハーバート・リードの『芸術による教育』を推奨しています。
教育における基礎訓練の重要性ということは、特に幼児教育の世界で際立ちます。だからこそ「基礎」訓練と言われるという側面もあります。マリア・モンテッソーリは「子どもは大人の親である」(その人がどういう幼児期を過ごしたかによって、その人がどういう大人になるかが決まってしまう)と言いました。また「ほとんどの大人は育ちそこない」であると言い、それが世界平和の阻害要因であると考えていました。しかし大人になってからの自己への気づきの重要性も強調されるべきでしょう。戦争が常態化した世界で平和をもたらす力は、依然としてひとりひとりの自覚にかかっているからです。
イタリア最初の女医で、幼児教育の科学的方法を開発したマリア・モンテッソーリは、ジョン・デューイも高く評価した教育者でした。『アヴェロンの野生児』を書いたフランスの医師イタールや、知恵遅れの子どもの教育法を開発したフランスの医師セガン(*)は、その先駆者として知られています。
* セガンについてはほとんど何の知識もありませんでしたが、学習院大学の川口幸宏先生のご教示によって、セガンはフランス人であること、アメリカに渡ったこと、資格の上では医師とは言えないこと(医学部未修了)などを知りました。以下を参照(2011年7月28日)。
http://www-cc.gakushuin.ac.jp:80/~920061/ http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~920061/200-1.pdf http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~920061/ikuryou30.pdf
アヴェロンの野生児は、赤ん坊のとき森に捨てられ、おそらく子育て中の狼によって森の中で育てられた子どもで、発見され見世物のようにされていたところをイタールに引き取られ、育てられて、その記録が残されました。頭のよい子だったようですが、人間の子どもが非人間的な環境の中で育てられると、その人間としての特性を発達させることができないという、当然のことを例証する結果となりました。(インドにもアマラとカマラという同様の例があったようです。)人間は発育の各段階で、それに見合う適切な環境を提供されないと、個々の特定の能力を発達させることができず、その能力を習得すべき時期を逸すると手遅れになってしまうということが確認されました。その時期を敏感期(sensible period)と言います。たとえば言語習得の敏感期に、言葉が話されない環境の中で育てば、言葉を話すことができなくなります。アヴェロンの野生児は結局「レ(ミルク)」という言葉しか話すことができませんでした。ミルクを飲むとき「レ、レ」と言ってはしゃぎましたが、その言葉がテーブルの上のミルクを指すということをどこまで認識していたか不明です。しかし書かれた文字を判読し、そのものを家の中から探し出してくることはできたようです。
動物学で敏感期に照応する言葉はcritical periodと言います。逸することのできない重大な時期という意味でしょう。コンラート・ローレンツ博士が発見した「刷り込み」理論はその極端な例です。卵から孵った雛は最初に見た動くものを「親」と認識します。もしそれが人間であれば、人間が親にされてしまいます。一旦、人間が親として刷り込まれてしまうと取り返しがつきません。そのような鳥は仲間を仲間として認知することができないので、生殖能力を失ってしまいます。第二次大戦後、上野動物園で人工孵化による鳥の増殖作戦が実施されましたが、ローレンツ博士の「刷り込み」理論をまだ知らなかったために失敗に終わったという話を聞いたことがあります。
セガンという医師は、知恵遅れの子どもの知能を発達させるために、特定の教具を用いた「感覚訓練」が有効であることを発見し、それを実践した人です。モンテッソーリはそれを知恵遅れの子どもだけでなく、健常児にも応用しました。(フレーベルはおもちゃのことをたしか「恩物」と呼んだのではなかったかと思います。)モンテッソーリは、子どもの遊びは遊びではない。成長のために必要な仕事であるという認識を持っていました。そして様々な教具を開発しました。子どもの成長に合わせて、適切な時期に適切な環境を提供するのは大人の責任であるというのが、モンテッソーリの基本的な教育観であったと思います。そして教育においては教師が子供に先ずそのモデルを提示(プレゼンテーション)しなくてはならないと考えていました。このモデルおよび手順の提示ということは、すべての教育理論の基本に据えられるべきことではないかと思います。(学習には模倣・認知・創造あるいは創作というプロセスがあって、初めに模倣があります。初めに模範が提示され、それを模倣するところから学習が始まります。天才も例外ではありません。)
モンテッソーリはまた子どもの発育の過程で、実に様々な「敏感期」があることを発見した人でもあります。敏感期には「集中」と「反復」という現象が起こります。その機能が完全に自分のものとなるまで、子どもは同じことに集中して、何度でもそれを繰り返します。たとえば同じ絵本を何度でも繰り返し読んでもらいたがります。それは言語習得の敏感期なのだからでしょう。秩序に対する敏感期には、たとえば家族がテーブルの同じ椅子に腰掛けることにこだわります。皆が決まった席につかないと怒ります。
モンテッソーリ教育が世界中で未だに根強い人気を保っているのは、それが科学的な根拠を持っているためではないかと思われます。動物に共通する身体的感覚的訓練に根差して、その上で言語と道具を使うという人間の特性を伸ばそうとしているからだと思われます。モンテッソーリはまた子どもに静寂(沈黙)の価値を教えようとした人でもありました。人間の人間らしさは2歳半頃にはもう決まってしまうという、幼児教育の重要性に注意を喚起した人でもありました。基礎訓練の大切さということを、この観点からも認識すべきではなかろうかと思います。
かつて“New Horizons”(“New Horizon”という中学校の英語の教科書ではありません)という英語教科書の編集者の講演を聞き、なるほどと思ったことがあります。それは現代の英語教授法の話でしたが、「現代の思考法」に通じるものがあると思いました。先ずその話を今の私の理解によってまとめれば次のようになります。
ノーショナル 言葉には様々な言い回しがあります。しかし表現は多様でも、要するにそれは「あいさつ」の文であるのか、何かを「辞退」するときの表現であるのかという具合に、概念(ノーション)でくくることが可能です。英語学習者はそのノーションを把握することによって学習を容易に進めることができます。
ファンクショナル 言語内行為か言語外行為という発話行為論にも通じることですが、表現は多様でも、要するにそれによって何がなされるのかに着目することによって、学習がはかどることになります。「今日はむし暑いね」と言っただけで、窓際の人が窓を開けてくれるかも知れません(言語外行為)。言語の実際的機能(この場合には「依頼」)に着目することが、やはり言語学習を容易にするための方法になります。
スパイラル 学習の原則は、単純なことから複雑なことへと手順を踏んで進んで行くことです。一度に一つの困難しか取り上げないで、単純なことから複雑なことへと、一つ一つ手順を踏んで実行していくならば、世の中には達成不可能なことは何もないと、アランは言いました。教育学者ルブールも、あるいはマリア・モンテッソーリも、「困難性の孤立(アイソレーション)」ということを言いました。単純な構文から複雑な構文へと、あるいはやさしい言い回しから難しい言い回しへと、スパイラル(らせん状)に進んで行くことは、英語学習の鉄則でもあります。
エクレクティック 世の中には様々な英語教授法があります。そのどれか一つに固執するのではなく、「いいとこ」取りをすること、あるいはその場に適切な方法を採用すること、場合によっては複数の方法を組み合わせることなど、教授法についてはエクレクティック(選択的)であることが望ましいことです。どんなに優れた教授法であっても、学習環境や学習者の置かれた状態を無視して、それを適用すべきではありません。
私がこの話は「現代の思考法」に通じると考えたのは次のようなことです。
発見的探究的思念的類比的方法論 発見的探求的であるとは思念的(ノーショナル)に何かを把握しようとすることです。あるノーションを獲得したならば、その問題についての見通しが与えられます。すなわち類比(アナロジー)の連鎖が成立します。ものを考えるときの基本は思念的であることです。そこに思考法の基本があります。
原理的開放的螺旋的反復的対話法 らせん的(スパイラル)に進行するとは、原理的でありつつ(原理がなければ思考は成立しません)、同時に開放的に(その原理に固執せずに)、他者との、あるいは事象との対話を繰り返し(反復的に)続けていくことです。だから原理は作業仮説の地位に留まっていて、いつでも修正可能でなければなりません。思考はある限定された事柄かららせん的に上昇して、次第に視界を広げていきます。
体系的規約的機能的構築的準拠枠 多くの思想家は体系構築的であろうとします。思想の一貫性を求めるためです。しかし体系はそもそも規約的(コンヴェンショナル)であって、機能的(ファンクショナル)な役割しか持ちません。それが便利であれば、その体系を採用するまでのことです。体系とは機能的な準拠枠(フレーム・オブ・レファランス)のことであって、それによってすべての現実を割切ることはできません。しかし思想を構築しようとするとき、その準拠枠として体系が求められます。
方法的領域的選択的合成的多元論 現代社会では方法的に多元的である必要があります。どんなに優れた方法であっても、それによってすべての問題が解決するわけではありません。またある領域に有効な方法も、別の領域では通用しません。だから人は方法的多元論というべき立場に立たざるを得ません。そして場合によっては、複数の方法を合成して(組み合わせて)事柄に対処しなければなりません。場面場面で、方法に対しては選択的(エクレクティック)である必要もあります。一つの方法しか持たないということは融通が利かないということでしかありません。狭い専門領域内でもそれは当てはまります。
発見的探究的思念的類比的方法論=原理的開放的螺旋的反復的対話法・体系的規約的機能的構築的準拠枠・方法的領域的選択的合成的多元論とは、要するにプラグマティズムです。純粋キリスト教(「純福音」)とか、純粋マルクス主義とかをイデオロギー的に主張する人からみれば、それはまことに不純な思想であるということになります。しかし今日事柄に即してものを考えようとすれば、それ以外のあり方は不可能ではないでしょうか。
ずいぶん前に読んだことなので正確な記憶はありませんが、ルドルフ・シュタイナーがどこかで「社会の三層化」ということを言っていたと思います。その意味は、宗教と経済と政治がそれぞれオートノミーを持っていて、互いに不当に干渉し合わない社会が健全であるという意味ではなかったかと思います。
今日の日本の社会を見ていると、まさにその正反対で、宗教と経済と政治の主導権が一個所に凝集していて、まことに不明朗な印象を受けます。いわば宗教的権威と経済的権利(利権)と政治的権力(私の言う三権)が一極に集中して、排他的な秩序が形成されつつあります。言い換えれば、政官業の癒着構造が靖国・護国神社の体制によって補強されつつあるような印象を持ちます。前にも述べた「権威は天皇に、権力は為政者に、権利は資本家にある」という反民主主義的な体制が益々表面化しつつあるように思われます。財力のある者が政治を動かし、それが宗教的伝統的権威によって補強されるという構図は、戦前への回帰であって、日本の支配層が戦後も一貫して手放さなかった「国体明徴」の理想です。それが戦後60年で漸く陽の目を見るようになったということなのでしょう。
それでは、その傾向に対置されるべき社会の三層化とは、果たして何を意味しうるでしょうか。日本の国家は一元的に支配されるべきであるということが一方の理想であるとすれば、それは「多元的社会」の第一歩であると言うべきではないでしょうか。しかし多元的社会の「模範」と目されていたアメリカに、やはり「三権」の一極集中という現象が見られるところからすると、それは何も日本に固有の現象ではなく、「保守主義」の表現形態であるように思われます。問題はそれが「戦争国家化(軍国主義化)」に帰結するということにあります。そして多数の民衆の福祉が捨てて顧みられないところにあります。
社会の三層化、あるいは多元化を推進する力は、どこから生まれて来るでしょうか。それは宗教・経済・政治のそれぞれの領域の「指導者」の自覚にかかっているというよりは、それらを下から構成している民衆の側の力量の問題ではないかと思われます。人々が指導者に指導されるがままの存在であるとき、国家社会の一元化が生じてくると言えるのではないでしょうか。しかし、指導(誘導)されてもそれに従わないということは、それほど簡単なことではありません。帰属とアイデンティティという「役割同一性」を越えて、ものごとを批判的に考える力は、日頃からの訓練によって養われます。ところが「体制に染まって」生きるということは、批判的に考えることをむしろ抑圧するということを意味しています。「指導者」は誰もそれを望んでいません。「依らしむべし、知らしむべからず」という権威主義者の格言こそが指導者の好むところであって、「体制」はそれによって維持されています。だから民衆の力量は、指導者が与える教育ではなく、民衆自身による教育によって育てられる必要があります。しかしそのような環境が整っていないところに問題があります。民主主義は、社会の構成員の側の、絶えずそれを育てていこうとする努力が伴わなければ、簡単に潰え去ります。
経済人が利潤を追求することはある意味で当然です。(しかしそこに何の倫理的拘束もないということであれば、大きな問題が生じてきます。)問題は、政治がそれを補完するために存在していて、国民全体の福祉を考えないところにあります。ましてや、天皇制によってその体制を補強しようというのであれば、それは国家の「タコ部屋化」であって、既得権を持つ者、「監視」の側に立つ者だけが得をする社会が生まれてきます。自由と平等の理想ははるかかなたに遠ざかっていきます。
社会の三層化を進めるためには、宗教においては信徒中心、経済においては労働者中心、政治においては生活者中心の立場に立つ必要があります(それが人民主権の内実です!)。そのような社会は一個の理想であって、直ぐには到来しないでしょう。しかし国家社会の一元的支配という国体論の復活だけはどうしても阻止すべきであると思います。それは破綻することがとっくに実証済みのファシズム以外の何ものでもないからです。
以下は人間を人間にしている四つの事柄を解明しようとする(手始めの)試みです。(私がやっていることは全部「手始め」のような気がします。私はそれを「生涯初心 life-long beginner」という言葉で合理化しています。)
理性 理性(reason)という言葉をどう理解したらよいでしょうか。それは個人のreasoning(推論)の能力であると言ってしまえばそれまでですが、人間になぜ理性が備わっているかと言えば、それは人間に言葉が与えられているからだと思います。日本語では理を「ことわり」と読ませます。要するにそれは「言葉の秩序」の問題です。だから言葉を離れては理性も存在しません。そして世界中にさまざまな言語があるように、理性も単一ではなく、言語の使用に応じて多様に変化します。ヒンドゥー教徒の理性があり、仏教徒の理性があり、イスラム教徒の理性があります。また物理学者の理性があり、医者の理性があり、漁師の理性があります。理性という単一のものがどこかに存在していて、それが人類の思考を支配していると考えるべき「理由(reason)」はどこにもありません。共通していることがあるとすれば、それは、言語は様々でも人間が言葉を使うということそれ自体の共通性であって、それは形而上学の問題ではなく、どこまでも実証的に解明されるべき問題です。しかし言語学や論理学や記号論などの多様な展開を見れば、人類に共通する理性の解明ということは、一筋縄では行かないことが判明します。だから理性とは「言葉の秩序」のことであると言っても、その秩序の多数性・多様性を前提にしてかからなければ、単純化のそしりを免れないでしょう。
体験 西田幾多郎は「我花を見る、このとき花は我、我は花である」と言いました。体験(直接経験)という「こと」の世界、主客未分以前の出来事は、言詮不及であると言うべきかもしれません。しかし通常、体験は言葉によって染め上げられています。人が存在と見なすものは、その意味で伝承されたもの(伝統)であって、純粋無垢の存在ではありません。存在は「用在」であって、人の目にそのように見えているということに過ぎません。何をどのように体験するかは、「存在の伝統」に属することであって、既に人間によって意味づけられた世界に属しています。先入主を離れて「事象そのもの」に触れるということは、人間にはおよそ不可能なことか、あるいは余程の修練を経た人が達する境地かの、どちらかしょう。通常は、体験は「存在の伝統」に属すると考えた方が事柄に即していると思います。そしてそこにもまた人それぞれの多様性があります。キリスト教徒は神を体験し、仏教徒は無に接します(「無」も言葉の伝承の問題です)。
功績 功績とは人が仕事を介して自分自身になっていく過程のことです。何かをすることを通して、自分が自分になっていく過程が、人の功績と言われます。つたい歩きしかできなかった子が、ひとり歩きできるようになることは、その子の功績です。功績とは、仕事を介しての「自己の実存(あるいは自己実現)」であると言えます。目覚しい功績もあれば、当然視されている「功績」もあります。しかし宮沢賢治が言ったように、歩けない者から見れば、大地の上を闊歩するのは奇跡に近い事柄です。「自己の実存」という人間にとっての理想の状態を観念的に表象することは無意味です。人は仕事という挑戦を通してのみ、あるいは冒険を通してのみ、自己の実存に達することを望むことができます。宗教改革の当時、プロテスタントとカトリックの間で、恩恵か功績かという論争がありました。その問題はおそらく「功績それ自体が恩恵に属する」と理解することによって解決するでしょう。功績が救いの交換条件にされる(外化される)ことが問題なのです。
啓発 古来「真理は伝えることができない」と言われてきました。自分がそのことに気づかなければ、周りで何を言っても無駄になります。啓発(enlightenment)とは、基本的に自己啓発のことであって、真理はその人自身に突然到来してくるかのような相貌を呈します。「真理の自証」(真理が真理自身を証明する)と言うべき事柄が生起します。まさにそれは心が照明(enlighten)されるような事柄を指しています。それは新しい秩序がその人自身の内部に立ち上がってくる事態(創発 emergence)であるとも言えます。教育が、基本的には自己教育であると言われなければならないのも、同じことを意味しています。宗教的な啓示と言われるものも、行為者としての神という実体が想定されていますが、それを受ける人の状態からすれば、啓発と同じことなのではないかと思います。突然、何ごとかが開示されてきます。発見(discover)とは覆い(カバー)が取り払われることを意味していますが、心の中でそれが起こるときには啓発と言われ、神が想定されているときには啓示と言われます。しかし「覆いが取り払われる」ということは必ずしも神秘的なことではなく、科学技術における発明発見のプロセスにもそれは起こります。それは人間の潜在意識に関わる事柄であって、多くの科学者がその機制を解明しています。