哲学の世界で範疇論と言えば、先ずアリストテレスの範疇論、次いでカントの範疇論があります。賀川豊彦はその著書のどこかで時代と思想が変われば、範疇は変わるべきものであるとした上で、自分の範疇論を展開していました。そこで前の「判断論」と関わらせて、私も私なりの範疇論を試みたいと思います。ただしこれは「試論」であって、なお検討しなければならないことが多々あります。
先ず私の「範疇表」を以下に掲げます。
様相範疇=実然性(必然性・偶然性)・蓋然性(決定性・可能性)
関係範疇=単子(性質・分量)・位相(時間・空間)
状態範疇=作用(結合・分離)・運動(能動・受動)
実然性(必然性・偶然性) 出来事の系列が必然的か、偶然的かということは、当然のことながら、その出来事に関わる主体の判断の問題です。それは前の「判断論」の信念(依拠)に関わる事柄です。私たちは大地に「信」を置いて暮していますが、突然の地震はその信を裏切ります。物理的にそれは必然の出来事でしょうが、地震を経験している本人にはたまたまそれが起こったと感じられるでしょう。外国旅行中に大地震に出会ったら、益々偶然それにめぐり合わせたと感じることでしょう。すなわち必然的か偶然的かということは、その出来事に出会う当人の視点の置き方の問題です。確実なのは今、現に私がここに居合わせているということです。
生きている主体にとっては、常に今、ここがあるだけです(そこから「永遠の今」などという思想も生まれてきます)。過去は過ぎ去ってもはやなく、未来は未だここに来ていません。アウグスティヌスが論じているように、過去は記憶において存在し、未来は期待において存在するだけです。アフリカに行こうが、アメリカに行こうが、日本にいようが、生きている主体は常に今ここで何かを知覚しています。つまり必然性と偶然性とは実然性の二様態なのです。現に今、私がここにいるからこそ、ある出来事が必然的であるか、それとも偶然であるかという問いが生じてきます。その問いはこの私の存在にも向けられます。父親と母親が出会って結婚したのは偶然のことかもしれません。しかしその結果として私が生まれてきたのは必然でしょうか。なぜ私が今ここに存在するのでしょうか。
未来が必然的に到来するのか、それとも偶然の所産として到来するのかという問いも生まれてくるでしょう。過去の出来事から外挿して、未来を思い描いても、それがその通りになるという保障はどこにもありません。すると未来に想定されるある出来事は必然的な結果なのでしょうか。それとも偶然の出来事が働いてそうなるのでしょうか。ただし人口予測などは相当の確度で言い当てることができます。日本の人口減はかなり前から予測されていたことです。すると物事によっては未来を必然的な結果として予測することが可能なわけです。だからある面では、単に運命に身を委ねるだけでなく、人間の努力次第では事態が改善されるという期待を持つことも可能です。現在だけが確かに存在するのだと言っても、それは未来に向けての努力を放棄してもよいということにはなりません。
蓋然性(決定性・可能性) 人口予測の問題に触れましたが、これは決定性・可能性の問題でもあります。実は、少子化時代になぜ自分が居合わせなければならないのかという問いから、それが必然であるか、偶然であるかという問いも生まれて来ます。しかし人口減の予測それ自体は「判断論」の言明(推定)に関わる事柄です。ある出来事が生じるのは、そうなるようにほぼ100%決まってしまっているからなのか、それともある程度の可能性を持つに過ぎないのかということは、信念(依拠)の事柄(ここから哲学的な存在の問題が生じてきます)ではなく、言明(推定)に関わる事柄です。
決定性・可能性というのは対立する二つの事柄ではなく、出来事が生起する確度として、高度の(たとえば100%に近い)蓋然性(決定性)を持つのか、それとも低度の蓋然性(可能性)を持つことなのかという、蓋然性の二様態であると考えてみます。つまり言明とは信念に基づく断定(断言)ではなく、すべて推定の事柄であると見なします。信念を取り払えば、言明はすべからく推定の問題であるというのが、ここでの論点です。
ただしここでは数学のように「必当然的」な推論、論証の問題を取り上げているのではなく、言明の蓋然性とは、「歴史的事実」に関わる物言いはどこまでも推定の域を出ないということを意味しています。(自然の法則と言われるものも、実は蓋然性の問題ではないのかとも考えますが、専門外の私としては発言を控えるべき事柄です。)
単子(性質・分量) 単子とはライプニッツのモナドのことではなく、ここでは性質と分量を持つとされる、個々のものという意味で使われます。何かが言い表されるとき、それが現実に存在するものであろうと、架空のものであろうと、ある性質と分量とを持っています。それがここで言う「単子」であって、言説空間は無数の単子で溢れています。
単子は、言表の外に存在するとされる「実体」ではなく、話題に上ることによって初めて存在するものです。話題にされなければ、それも存在しません。単子はボキャブラリーの内側に存在するものであって、その外に存在する何かではありません。虹は七色であるというのは「客観的な」真理ではなく、ある民族にとっては十色かも知れず、他の民族にとっては三色かも知れません。
科学的な真理は、科学者の集団の中で、科学的な言説において存在します。そこにはマイケル・ポラニーが指摘するように、科学の伝統と言うべきものがあります。それが失われれば、「科学」は資本の餌食となり、利益に結びつかない研究は顧みられなくなるでしょう。あるいは「創造科学」などという、宗教によって利用される捏造された知に変身してしまうことにもなるでしょう。だから単子は言表の内部に存在すると言っても、そこには何の基準もないということではありません。
知は「人称的な知(personal knowledge)」であって、言説空間の内部に存在します。そして、ある特定の言説空間において知られる個々のものが単子と言われます。単子は人称圏の多様性に応じて千変万化します。「人権」はある人にとっては守るべき基本的な価値であり、他の人にとっては唾棄すべきイデオロギーの所産であるということになります。「ジェンダー」についても同様です。
位相(時間・空間) 時間と空間とを統一する概念はありません。位相(トポス)は空間的な概念であって、時間を含んではいません。しかしここでは時間と空間とが重なり合い、一致している「点」を位相と呼ぶことにします。無数、無限の「今、ここ」が位相であると考えてみます。位相は、過去、現在、未来の無数の頭数の人間の、そのまた過去、現在、未来にわたって、無限に折り重なって存在しています。
単子は位相において多重に、折り重なるように存在しています。個々の単子の同一性と差異性は、それが持つ性質と分量、ならびにそれが占める位相によって決まります。そこに、あるものをそのものとして同定し、他のものを他のものとして異化する判断が成り立ってきます。あるものは同類として包摂され、他のものは異物として排除されます。
位相を社会空間、あるいは歴史的社会空間として見るならば、そこには包摂され、あるいは排除される、人間集団の多重の重なり合いが見られます。そこに歴史のダイナミクスがあります。
繰り返して言えば、単子と位相とは、人間が物事を同定(包摂)し、異化(排除)する「判断」の構成要素であると見なされるべきものです。
作用(結合・分離) 何かを結びつけ、あるいは切り離す働きを作用と呼びたいと思います。たとえば思考作用は表象を結合し、分離する働きです。それは思考の化学反応のようなものです。二つの表象が結合することによって、何か別のものが生まれてきます。あるいは今まで結び付けていたものを切り離すことによって、別の展開が可能になります。判断の基礎には、この結合と分離があります。
作用を意識的に引き起こすためには、方法(手順)が求められます。フランスの教育哲学者ルブールは「学習」の方法を次のように定式化しています。
① 模範(モデル)を意識する。
② その模範を、それを構成する一つ一つの行為に細分化する。
③ その個々の行為を一つ一つ実行する。
④ それらの行為を元の模範の形に再結合し、無駄な動きがなくなるまで、反復吟味する。
つまり、何かが上手に(巧みに、うまく)できるようになるということは、無駄な動きがなくなるということを意味しています。それは習熟度(プロフィシエンシー)の問題です。習熟度はその程度が評価(質的に判定)されます。
技能だけではなく、思考においても習熟度が問われるでしょう。何度も同じことを考え続けることによって、いわば思考が熟してきます。思想も訓練されるべき事柄です。
運動(能動・受動) 運動とは、先ずもって位置の移動のことです。移動は、抵抗とエネルギーの問題です。そこに能動と受動、動と反動ということが伴ってきます。
運動は人間が身体的な存在であることから生まれてくる概念です。そこから転じて、「社会運動」のように比喩的な使い方もなされるようになります。
仕事、あるいは労働も、比喩的に言えば、人間の意識的な運動であると言えます。しかし意識的な運動は、普通、行動と言われます。そして仕事量は、その仕事に伴う抵抗とエネルギーによって決まってきます。既に作用のところで動きに触れたように、人間の意識作用の根底に運動(行動)があります。思考は行動の延長であると見なすべきものです。
仕事の効果(成果)、あるいは達成度(アチーブメント)は、量的に測定されます。学習の成果も、企業のパフォーマンスもその点では同類です。
しかし今日のような「反動」の時代には、それを覆すべき「社会運動」のことがどうしても私の念頭から離れません。体制側の策動に対する民衆の側の抵抗とエネルギーが問われています。守勢から攻勢に転じる(攻守ところを変える)にはどうしたらよいのでしょうか。
ゼーションというのは、今田高俊という社会学者が用いた言葉です。インダストリアライゼーション(工業化)のように、社会変化を表わす英語には「ゼーション」がついているところから来た「和製英語」です。
三つのゼーション現象というのは、世俗化(外在化)・制度化(物象化)・専門化(資格化)という近代化を特徴づける三つの現象を言い表すものとして、私が勝手に使っている言葉です。以下、これについての若干の考察を試みます。
世俗化(外在化) 近代化(西欧化)の底流にあるものは世俗化です。それは資本主義社会の興隆と密接に関わる事柄で、客観的な指標で定量できるものだけをリアルであるとする態度(傾向)を表わすものであると考えます。アメリカ社会に顕著であると指摘されてきたこの傾向が、今や世界的に広がっています。たとえば、自分の大学がいかに優れているかを示すのに、教授陣にノーベル賞受賞者が何人いるか、研究費の総額はいくらで、教員一人あたりの研究費はいくらになるか、教員一人あたりの学生数は何人であるか、校地の面積はどれだけあるか、そこに樹木が何本植わっていて、ベンチが何個置いてあるかといった言い方をします。確かにそれは優秀さを示す一つの指標ではあります。ある価値を言い表すために、量的な指標だけが用いられるそのような傾向を外在化、あるいは価値の外在化と呼べるのではないかと思います。
これは抗いがたい傾向として存在します。救済財という精神的価値によって成り立つ筈の教会でも、信徒数は何人いるか、献金総額はいくらであるかといったことを問題にせざるを得ません。学校も卒業生の就職率や進学率、資格所得率などを売り物にしなければ、学生募集に差し支えます。しかしそのような傾向が社会全体を覆うとき、そこから抜け落ちてしまうものが何であるかを考えて見ることは、きわめて重要であると思います。
そこから抜け落ちてしまうものは、言ってみれば、当事者の個別意識であり、個々人の特異性です。あるいは地域性です。個性や地域の特性が捨象されて、のっぺりした砂地のような空間が広がって行きます。数字だけがものを言う社会が生まれて来ます。業績は数字で示さなければゼロに等しいものとなります。教師も一人の生徒の問題にかまけていては、教育の「実績」を示すことができなくなります。生徒も「成績」を上げなければ、「負け組」の烙印が押されてしまいます。
そのような傾向のもとにある社会では、達成度だけが問われて、習熟度が問われなくなります。仕事の量だけが問題にされ、仕事の質は顧みられなくなります。学者は論文の数だけで評価されるようになります。企業はパフォーマンス(成果)を上げることだけを追求し、企業倫理などはどこかへ行ってしまいます。テレビ局では視聴率がものを言い、番組の内容は問われなくなります。新聞雑誌も購読者数だけを競います。政治家は自分の「人気」と支持者や仲間の「人数」だけを競い、その「任務」の遂行を怠ります(あるいは本当の意図を選挙民の目から隠そうとします)。
市場原理主義はそのような社会的傾向の当然の帰結です。それは社会の量的あるいは商業主義的な「平準化」を促進します。それに対抗するかのように見える宗教原理主義や伝統的保守主義も、社会のほころびを取り繕う補完物として、今や市場原理主義者によって利用されるものでしかありません。そこで持ち出される宗教や伝統はきわめて強圧的で、かつ平板化しています。新自由主義が権威主義的に補完されなくてはならないというところに、今日の社会の限界(あるいは矛盾)が露呈しています。
制度化(物象化) 制度化とは人間関係の物象化です。官僚制や軍隊の機構にその極致があります。マックス・ウェーバーがつとに指摘したように、近代の社会組織は官僚制化の傾向を免れません。組織に嵌め込まれた個人は、歯車として機構の一部を担うだけの存在となります。位階制(ヒエラルキー)によるピラミッド的な組織図が企業集団にも適用されます。民主主義が名目化してしまうのは、上意下達の官僚機構が社会組織の中枢を占めているからです。最近、東京都の公立学校で職員会議の採択を禁じる通達が下され、問題になりました。官僚制的な管理社会化の傾向が公教育の末端にまで行き渡ろうとしているということなのでしょうか。
トップダウンではなく、ボトムアップの社会組織論があったとしても、社会の大勢が官僚機構によって支配されているところでは、精々その穴埋めとしての役割しか果たすことができません。各種のボランティア活動が地方行政によって奨励され、赤字財政で行き届かない行政サービスの欠を補うものとされつつあるのは、その一例です。
ヒト(人的資源)・モノ(物的資源)・カネ(財的資源)・コト(情報資源)が物象化された世界の構成要素です。コトとは出来事のコトであり、同時に言葉のコトでもあります。つまり情報のことです。それにトキ(時間資源)・トコロ(空間資源)も加えるべきでしょう。既にフランクリンが「時は金なり」と喝破している通りです。ロケーションの経済価値については言うまでもありません。
すべてが物象化された世界では、「能力」・「納期(〆切)」・「能率」がものを言います。能力とは時間内に(〆切までに)、正確に仕事を仕上げることができるという意味です。能率とは、正確かつ迅速であることを意味しています。制度化された社会ではそれだけが求められます。それが何のためであるかという問いは封印されています。そこから「精神なき専門人」が登場してくるのは当然というものです。
専門化(資格化) 専門化とは分業のことです。人は自ら専門化し、特化しなければこの社会で生きていくことができません。その専門性を示す指標として資格がものを言います。今は何でも資格の世の中に見えるのはそのためです。
資格は人の専門性も物象化されているということを表わしています。資格も金で買うべき時代となりました。普通は学校に授業料を払い、資格を身につけようとします。しかし短絡的に実力がなくても資格を金で買おうとする人まで現われてきます。
資格の発行主体が誰であるかも問題です。同業者の「ギルド」が資格を付与するのではなく、多くの場合、行政が資格を付与します。行政の許認可権がここにも顔を出して、行政権力を強化することに貢献しています。教員資格は行政によって付与されます。最近、行政が好ましくないとみなす東京都の教員が分限免職の処分を受けました。行政が定めた規律が公立学校の教員資格の要件とされていることを示すものです。
裁判官、外交官という公務員の資格も「行政の規律」に従うことを前提として付与されていると思われます。その行政の規律には、今では、過激派(あるいは社会の不穏分子)であれば、法廷での判決や警察署での処遇において法規や人権も無視されて構わないとか、時の首相の意思(政策)に逆らうことは外交官として許されることではないとかいう判断も含まれているようです。
それらの例は、資格の公的基準とされているものが、憲法に準拠するのではなく、公権力の意向に沿うものであるか否かということに置かれていることを示すものであるように思われます。ここにも憲法と民主主義の形骸化が進行していることの一例があるように思われます。
デイビッド・E・クルーギー教授は『外国語の授業における共働学習―日本の中高等教育におけるEFL(外国語としての英語教育)の状況のための分析と提案―』(金城学院大学論集(英米文学編)第34号(通巻第149号)1993年3月)において、協力的学習の論拠として、以下の三つを挙げています(以下拙訳)。
1.ヴィゴツキー(Vygotsky)の「近接的発達領域の理論」
ヴィゴツキー(1988、注略、以下同様)は学習と発達との間の諸関係、特に発達のサイクルを研究した。彼は発達の二つのレベルを理論化した。一つは現実的発達のレベルで、「いくつかの既に完了した発達のサイクルの結果として確立されている、子どもの知的機能の発達のレベル」と定義されている。たとえば伝統的なIQテストで確認されるようなレベルのことである。他は潜在的発達のレベルで、これは子どもの知的機能発達のレベルであるが、いくつかの未完了の発達のサイクルの結果として確立されているものである。ヴィゴツキーは近接的発達領域を「独立した問題解決によって決定される現実的発達のレベルと、大人の指導のもとでの、あるいはより有能な仲間たちの強力による問題解決を通して決定される潜在的発達のレベルとの間の距離」と呼んだ。
ヴィゴツキーは述べている。「今日、子どもたちが一緒でならできることは、明日はひとりでもできる」。あるいはエルボー(Elbow)が書いたように、「初めはほかの人たちと一緒のときにだけできたことは、ひとりでもするように学ぶことができる」。
2.ウィットロック(Wittrock)の「認知的練成の理論」
ウィットロックは、人は何かを教え、説明するときに、最も効果的に学ぶものだということを理論化した。彼はこれを認知的練成あるいは認知的再構造化と呼んだ。この理論を確認するため、最近の研究は、人々はほかの人たちに教えることの95%を学ぶものだということを示した。
3.ドイチュ(Deutsch)の「目標に到達するための諸構造」
1949年にドイチュは、教室における、協力的、競争的、個人的の、三つの異なる目標構造(goal structure)を確認した。協力的目標構造においては、各人の達成はほかの人たちの目標に貢献する。競争的目標構造においては、各人の達成はほかの人たちに否定的な影響を及ぼす。個人的な目標構造においては、各人の達成はほかの人たちに何の影響も及ぼさない。ドイチュの仕事は、教室における協力的学習についての、多くの実験的な研究に対する根拠として役立った。
協力的学習の理論的根拠についてのこれらの指摘は、ガキ大将から味噌っかすまでを包含する、昔の子ども社会のことを思い出させるものです。しかし同時に、協力的学習は大人の社会においても適用されるべきものではないかとも思わされます。私は「実践的学習共同体」とでも言うべきものを構想していますが、それについては稿を改めて論じることにしたいと思います。
実践的学習共同体(Practical Learning Community)の一例として、憲法改悪に反対する意志を共有する人たちの「学習会」を想定してみます。その場合、基本的な事柄として何が求められてくるか、あるいは何が問題になるかを考えてみます。
1.コーズ・コミットメント・インドゥエリング(CCI)
コーズ コーズとは、なぜその学習会を立ち上げるのかという根本原因のことです。why-becauseのbecauseはby cause that (~という理由で、~という原因で)を意味しますが、先ずそのコーズが明らかでなければ何事も始まりません。今の場合には、憲法「改悪」の動きに危機感や疑問を感じているということがコーズになります。このコーズが共有されなければ、そもそも学習会が始まりません。ただし憲法を変えることに賛成の人も、反対の人も、存分に議論を交わす場をつくりたいということがコーズである場合もありえます。そのときには会の性格が変わってくることになります。
コーズは経営学で「大義」と訳されているようです。「平和」や「戦争反対」が学習会のコーズとして確認されている場合には、単なる危機感や疑問を越えて、それはまさに学習会の「大義」であると言うことができます。
コミットメント 学習会では、現行憲法の条文、その成立の歴史的背景、今日までの改憲運動の流れ、現行憲法と自民党改憲案との比較対照など、学習課題が提示されます。参加者はそれらの課題に自らコミットすることが求められます。辞書を引くと、commit oneself の意味として、①(道義的・法律的に)身を縛る、言質を与える、(引っ込みのつかぬ)約束をする、コミットする、②(実行を伴う問題について)態度〔意見〕を表明する、とあります。ここでは②の意味に限定するとしても、「実践的」学習共同体においては、学習者は個々の問題について(直ぐにではなくても)はっきりとした態度を表明することが求められます。
実はここに一つの関門があります。政治がテーマの学習会においては、往々にしてある政治的党派が背後にあり、その党派の見解が学習会を方向づけているということがあるからです。それは措くとしても、多くの人はそもそも政治的なテーマについて態度を決めることに、それが反体制的な意思表明につながるのであればなおさら、躊躇を感じるものだからです。これは宗教的テーマの学習会についても言えることです。人が教会の聖書研究会に参加することにためらいがちなのは、いずれ「信仰告白」を求められるであろうという「恐れ」を感じるからです。カルチャーセンターの聖書講座に参加しやすく感じるのは、この態度表明を迫られなくて済むからです。
インドゥエリング その関門を潜り抜けたところに漸くコミットメントが成り立ちます。そして学習会で学習活動を続けることによって、学習すべき内容が次第に自分の頭の中に入ってきます。マイケル・ポラニーはその過程を「内住、インドゥエリング(in-dwelling)」と言います。動物行動学者ローレンツ博士の言う「刷り込み(in-printing)」ほど極端な過程ではありませんが、学習すべき事柄に学習者は次第に「住み込む(dwell in)」ようになります。学習とはこの参入(participate in)のプロセスです。馴染みのなかった事柄に段々馴染んでくる過程であると言うことができます。今の場合には、憲法が身近な問題として認識されるようになるということを意味します。
ここで言う内住あるいは参入と洗脳(マインド・コントロール)とはどこが違うかという難しい問題があります。内住においては合理的な判断が排除されないどころか、それが奨励されるが、洗脳においては合理性が棄却されていると一応は言うことができます。しかし不合理と知って、敢えてその事柄に参入する場合があります。信仰には往々にしてそういう側面が見られます。古代教父のひとりテルトリアヌスが言ったとされている、「不合理なるゆえに、我は信ず」という言葉が知られています。改憲派(往々にして国家主義者)が宗教教育を重んじたがるのは、自分たちの主張の根拠が合理的ではないということを認識しているためではないかと思われます。
2.コミュニカティブ・アンド・コーパラティブ・ストラクチャーズ(CCS)
社会的相互作用には様々な構造があります。社会的相互作用の一つである学習会にも様々な構造、あるいは形式が知られています。目的や参加者の人数によっても規定されますが、その形式には、シンポジウム、パネル・ディスカッション、バズ・セッション、セミナー、話し合い(グループ・ディスカッション、グループ・カウンセリング)、講義、講演などがあります。
あるいは講師が存在するか、インフォーマント(情報提供者)はどうか、議長・座長がいるか、コーディネーターはどうか、あるいはむしろ全員にリーダーシップが期待されているかという観点から、学習会の構造を論じることも可能です。
前の項目で取り上げた「協力的学習」理論においては、開発された特定の「諸構造」が存在しており、クルーギー教授は特にそれを用いる協力的学習のことを大文字でCooperative Learningと表記しています(拙訳では「共働学習」)。
コミュニケーションを促進し、協力的学習を展開するための諸構造(コミュニカティブ・アンド・コーパラティブ・ストラクチャーズ)は、今まで知られていて実践されてきたもので十分であるというわけではありません。グループワークの方法論として今後も意識的に開発されていくべきものです。ここでは前掲のクルーギー論文の付録にある11の共働学習構造の諸例から、2例(細かくは4例)のみをご参考までに紹介いたします。
① ジグソーⅠ
ステップ1 各々の学生はあるトピックについてのエキスパートになる。
ステップ2 学生たちは彼らの情報を分かち合う。
② ジグソーⅡ
ジグソーⅠと同じ。ただしすべてのメンバーが同じ情報を持つ。各人は、その情報によってなされなくてはならない、ある課題についてのエキスパートである。
③ チーム・ジグソー
ステップⅠ 各人は「ホーム・チーム」に属する。
ステップ2 各人はそのチームで番号を割り当てられる。
ステップ3 どの番号の人も「マスタリー・チーム」(同じ番号を持った人たちの集まり)に行って、ある情報、あるいは課題をマスターする。
ステップ4 各々の学生はホーム・チームに戻って、情報(課題)を分かち合う。
④ Co-op Co-op (二段重ねの協力)
ステップ1 クラス全体で、学生たちはトピックについて、彼らが既に知っていること、知りたいと思うことを議論する。
ステップ2 クラスはチームに分かれる。
ステップ3 各チームはチームづくりの練習を行なう。
ステップ4 各チームはステップ1からトピックを選ぶ。
ステップ5 チームはサブチームに分かれて、ステップ4で選ばれたメイン・トピックの、ミニ・トピックを選択する。
ステップ6 各々の学生はミニ・トピックを研究し、チームに発表する準備をする。
ステップ7 各サブチームはチームに発表する。
ステップ8 チームはクラスへの発表を準備する。
ステップ9 各チームは彼らの発表を行なう。
ステップ10 発表が評価される。
3.協力的学習からVAINへ
学習会を敢えて「学習共同体」と言ったのは、協力的学習が意識的に遂行されるところにコミュニティ(共有価値によって成り立つ社会集団)が形成されてくると考えるからです。しかしそれは必ずしも一枚岩の集団がつくられるということではありません。様々な側面での個々人の違いは、簡単には乗り越えられないものとして、最後まで存在します。そのような相違があるにも拘わらず、なおその集団のコーズやミッション(使命)が、絶えず新たに確認され、共有されていくところに「実践的学習共同体」の存立がかかっています。一言で「平和」、「反戦」と言っても、状況の変化や認識の深まりに応じて、その意味も多様に変化します。コーズは中空に浮かんでいるのではなく、絶えず変化する実践的課題のうちに見出されるべきものです。
教会の教義や政党の綱領のようなものが、未だに人々の行動を縛っているように見えます。しかし私は「実践的学習共同体」をもっと開かれた場として構想しています。ネグリ・ハートが指摘しているように、前衛と大衆という構図は今日では益々意味をなさないものとなりつつあります。教会(選ばれた民)と異邦人(まだ救われていない人たち)という図式も同様にその意味を失いつつあります。
実践的学習共同体は上からの指令で組織されるものではなく、人々の自発的結社(ボランタリー・アソシエーション)として形成されるべきものです。だからそれは多様な展開と広がりを持つべきものです。そこからVAIN(ボランタリー・アンド・インテレクチュアル・ネットワーク)が社会に網の目のように張り巡らされて行くことでしょう。
七つの哲学的用語というのは、定位・規定・限定・止揚・還元・構成・措定のことです。これらの七つのタームから何が示唆されるのか、それを人間の生き方の問題として考えてみたいと思います。
定位・規定・限定 定位(orientation)という言葉は七つの用語の中では、唯一、哲学ではあまり使われない言葉です。生物学で、生物体の一定の位置、姿勢を示すものとして使われているようです。広辞苑には、生物体が体の位置または姿勢を能動的に定めること、また、その位置または姿勢、と書かれています。
獲物に飛びかかろうとする動物の姿勢を思い浮かばせる言葉です。しかし人間の場合にもどこに居場所を定め、何をどうしようとしているかということは、根本的な意味を持つことではないかと思います。定位において、実践主体は初めて理論的な規定を受け、また実践的に限定されるものとなります。企業の経営者になれば、自ずとその立場は理論的に規定され、実践的に限定されることになります。あるいは逆に、その立場から積極的に状況を規定し、また限定しようとすることでしょう。
限定と規定とは同じ意味に使われることもありますが、ここでは限定 determination、規定(規制)regulation の意味で用いたいと思います。規定は集合的理性に関わる事柄です。理性はもともと集合的だと思いますが、自己を(社会的に)定位する、あるいは自己が(社会的に)定位されるということは、その立場を理性的(理論的)に規定する、あるいはその立場が理性的(理論的)に規定されるということを意味します。同様に、自己を(社会的に)限定する、あるいは自己が(社会的に)限定されるということは、その立場を実践的に限定する、あるいはその立場が実践的に限定されるということを意味しています。立場が変われば異なる規定と限定がなされるでしょう。つまり規定と限定とは(自己)定位において相対的に働きます。
企業において労働者は経営者の労働についての規定と限定に従うだけでしょうか。労働者が自己の労働についての規定と限定を行なうという権利は存在しないのでしょうか。ここに労使関係の問題が生じてきます。これはもちろん一つの例であって、社会的自己定位には、職業的自己定位、家族的自己定位、性的自己定位、市民的自己定位、国民的自己定位などと、複雑に絡まり合って存在しています。その都度、異なる規定と限定とがなされるでしょう。そこには「絶対的」自己定位なるものは存在しません。
一つの主義主張、あるいは信念が、すべてを規定し、限定し尽くしてしまうなどということは、ありえないことですし、あってはならないことです。しかし人間の世界ではそのような思想(イデオロギー)が往々にして力を揮います。それはキリスト教だったり、マルクス・レーニン主義だったり、国家主義だったりします。今日の日本では天皇制的家父長主義的国家主義が再び頭をもたげようとしているのではないでしょうか。
還元・構成・措定 定位・規定・限定という社会的な「枠」の中で、還元・構成・措定という個人的な思考作用が生じてきます。
フッサールの現象学的還元を正確に理解することは困難です。またその立場にも変遷があります。ここでは還元を個別的経験の自己省察、あるいは単純に自己認識の意味で用いたいと思います。
還元において現象学的記述がなされますが、フッサール自身、純粋に現象学的記述を貫いているわけではなく、そこにはある種の構成が働いているという指摘があります。記述的様式には規範(端的に言えば文法)が伴っており、そこから自由に何かを記述することは、そもそも不可能なことです。構成は、還元に並んで、それ自体を主題として論ずべき事柄ではないかと思われます。そこから言語分析というもう一つの哲学的な課題が生じてきます。それは記述的様式の規範分析と言うべきものです。
またフッサールは対象の実在性を括弧に入れると言い、意識の志向性それ自体に注意を向け直そうとします。対象を対象として固定する働き(措定)それ自体を問題にするということは、内省の極致と言うべきもので、東洋的な瞑想の行を思わせます。
ありていに言えば、還元とは「ふとわれに帰る」というときの、われに帰る心の働きであり、構成とは自分の考えを(言葉で)組み立てることであり、措定とは今注意を向けているそのもののことです。人間がものを考える存在である限り、必ずこの三つの働きに与っています。それは個人の心の働きですが、社会的に枠づけられています。
止揚 止揚(揚棄)というヘーゲルの用語は近頃あまり使われません。それに換わって、創発、自己組織化などという言葉が使われます。簡単に言えば、カオスから新しい秩序が立ち上げって来るという意味だと思います。
私としては、抑圧・分裂・対立・離反の現実において、解放・統合・融和・一致を実現していくプロセスとして、止揚という言葉に魅力を感じています。個人的な努力においても、
発明発見、あるいは創作には、単に創発、自己組織化という側面だけではなく、葛藤を乗り越えていくというプロセスがあるのではないかと思います。つまり対立が止揚されて、新しい地平が開かれてくるという側面があるのではないかと思います。
定位が人間の生き方の根本原理であるとすれば、止揚はその中心原理と言うべきものです。あるいは止揚とは歴史形成に関わる原理であると言うべきでしょう。
以下は田邊元の『哲学入門 哲学の根本問題』(筑摩叢書55、1966)に出て来る、哲学を区分するための図式(見取図)です。外側の大きな正三角形の頂点にA、B、Cを配置し、内側の小さな逆三角形の頂点にD、E、Fを配置し、A―F、D―B、C―Eの線が交わる正三角形の中心にGを置きます。
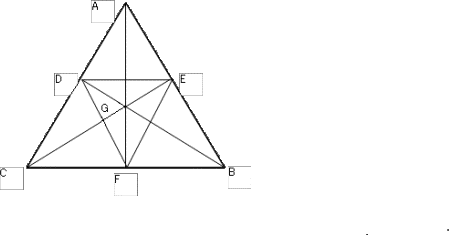
田邊はAに神學(宗教哲學)、Bに〔理論〕認識論(自然學)、Cに〔實踐〕倫理學、Dに美學(芸術學)、Eに歴史哲學、Fに形而上學(存在學)、Gに政治哲學を配置しています。
その昔、私は田邊のこの図式に大いに啓発されました。この図式に私はA=宗教哲学(解釈学的存在論・超越的実在の存在了解)、B=社会哲学(類型論的構造論・集合的理性の形成過程)、C=実践哲学(人間学的倫理学・全体的人間の実存分析)、D=文化哲学(現象学的認識論・個別的経験の自己省察)、E=言語哲学(文体論的分析論・記述的様式の規範分析)、F=自然哲学(分類学的存在論・対象的実在の一般法則)、G=歴史哲学(弁証法的存在論・総合的実在の発展段階)を配置し、それを指針として、哲学を自己流に、ささやかながら勉強してきました。
田邊の図式のうちに既に見られることですが、私はA―Bの線を理論系列(構文論的系列)、A―Fの線を存在系列(意味論的系列)、A―Cの系列を実践系列(語用論的系列)と見なしています。すなわち記号論の三分科にやや強引に照応させています。そしてAを哲学の根本原理、Gを中心原理と見なしています。
この図式は一種のマンダラです。哲学のあらゆる問題(世界のすべての現象)はその中のどこかに当てはめられます。また整理棚のようにあらゆる知識がこの中のどこかに仕舞われることになります。そしてAからGの領域で何か一つの問題を取り上げると、あとは芋づる式にその問題は他のすべての領域に繋がりを持ってきてしまいます(この図式の一番重要な意味はここにあります)。
その後私はこの図式を哲学の区分以外の色々なことに利用してきました。前の項目で取り上げた「哲学の七つのターム」は以下のように配置されます。
A=定位・B=規定・C=限定・D=還元・E=構成・F=措定・G=止揚
また「思想について」の最初の項目で取り上げた英語教育の七つの原理は以下の通りです。
A=コミュニケーション、B=社会的相互作用、C=文脈化、D=反省的学習、E=学習のスタイル、F=聴くことが土台である、G=学習者中心
これからも田邊の図式の応用編を取り上げる予定でいます。今後私はこの図式のことを、田邊のTと閑老人のHを取ってTH図と称したいと思います。
三一致の法則と言ってもドラマのつくり方のことではありません(ドラマの場合には確か時間と場所と登場人物の一致のことだったと思いますが…)。かつて職場の上司からshould・could・wouldの一致という話を聞いて、なるほどと思ったことがあります。
何かをしようとするとき、先ずIf I should…と自分に問いかけます。そしてそれをすべきであるとしたら、次にIf I could…と自分にそれができるかどうかを考えます。しかしたとえなすべきであり、なしうるとしても、If I would…と本当に自分がそれをしたいと思うかどうかを確かめます。その三つが一致したとき、初めてそれをなすべきであると言います。
カントは「汝なすべきがゆえになし能う」と言いました。また孔子は「我が欲するところに従って則を越えず」と言いました。確かにshould・could・wouldの一致ということは、人間が何かを行なおうとするときの指針であると言えるでしょう。
しかし社会の大勢に逆らってそれを変えようとするときには、この三つの問いはたちまち困難にぶつかります。たとえなすべきであると考えても、couldとwouldについては否定的な結論に傾きがちだからです。shouldだけで行動するということには無理が伴います。自分を押し殺さなくては行動することができません。そしてそのような行動は長続きがしないはずです。その挙句、自分に課したshouldの結論自体があやしいものとなるでしょう。
shouldの結論は往々にしてイデオロギーの所産として与えられます。キリスト教やマルクス・レーニン主義などがその人に「大義」として与えられているから、それに従って行動しようとします。しかし多くの人たちがそれに従おうとしないのは、その人たちの三一致の法則に逆らっているからです。人はshouldだけでは動きません。
権力はこの法則を逆用します。社会運動を警察権力によって威嚇し弾圧することによって、人々のcouldとwouldの希望を打ち砕こうとします。そして多くの人たちは「長いものには巻かれる」生き方を選択します。その結果、益々「生きにくい」社会が到来するとしても、それ以外に選択の余地はないと考えるようになります。そこまで追い込まれてしまえば、むしろ権力が与える「大義」に喜んで従おうとするでしょう。そして「天皇陛下万歳」を唱える社会が再びやって来ることになるでしょう。そこにこそshould・could・wouldがあると思ってしまいます。
私自身が今、上に述べた困難に直面しています。そして私を動かす「コーズ(大義)」をまだ明確に把握してはいません。キリスト教やマルクス・レーニン主義はもはや私を動かす「大義」ではありません。脱イデオロギー的な人間で、かつ体制側の策動に乗りたくないと思っている私のような人間に一体何ができるのでしょうか。「閑老人のつぶやき」はそこから始まります。私自身が本当に追い詰められていないから、そして困っていないから、つぶやく「余裕」も生まれて来るのでしょう。しかしそこからどんな行動が生まれて来るでしょうか。
つぶやきが叫び(「荒野で叫ぶ声」)になるために、私には欠けているものがあります。足りないことがあります。「あなたに足りないことが一つある。帰って、持っているものをみな売り払って、貧しい人々に施しなさい。そうすれば、天に宝を持つようになろう。そして、わたしに従ってきなさい」(マルコ10:21)。
プロフェッショナル・スクールの一つとしてのMBA(経営大学院)が日本の企業からも注目されるようになって久しいものがあります。また世の中には様々な経営理論が氾濫しています。しかしかつては、学校、病院、社会福祉団体、青少年団体あるいは教会など、NPOと称される団体は、営利組織(PO)すなわち企業の経営理論や手法を導入することに対して余り積極的ではなかった面がありました。それは「利潤追求」のための理論や技法を取入れるのは不純かつ異質であるという理由からだったと思われます。
しかし今日では大分様子が変わってきました。ドラッカーがつとに指摘しているように、少なくとも以下の2点が考慮されるようになったからでしょう。
1)NPOもPOも、組織であるという点では変わりがない。従って組織運営に関しては、かなり共通する面が多い筈である。「利潤の追求」ということに関しても、この資本主義社会では、利潤は企業がその生産活動を通して社会に貢献する度合いの指標であり、企業の存続とイノベーションのためになくてはならないものと考えるべきである。非営利組織においても、赤字の経営が続けば、その存続は不可能である。また、少なくとも形式的な側面から見るならば、組織運営の基本である、使命の達成ということに関しても、両者には共通するところがある。
2)NPOは、会費、寄付金などの「浄財」によって運営されている。だから折角の資金を一銭も無駄にしないよう、組織の運営に関してPO以上に厳格な管理がなされるべきである。そしてそのためには企業の経営管理の方法から学ぶべき点が多い。
そこで、先ず、この方面で古典的な著作となりつつある、ドラッカーの「非営利組織の経営」の内容を目次で確認してみます。
ピーター・ドラッカー「非営利組織の経営」[Ⅰ部]使命が第一…リーダーの役割
1. 使命とは何か
2. リーダーはどうあるべきか
3. 目標の設定(対話)
4. リーダーが負うもの(対話)
[Ⅱ部]使命から成果へ…マーケティング、イノベーション、資金源開拓の効果的戦略
1. よき意図を成果に結びつけるには
2. 勝つための戦略とは
3. 市場を定義する(対話)
4. 寄付者という支持層を定義する(対話)
[Ⅲ部]成果をあげるためのマネジメント…成果をどう定義するか、どう評価するか
1. 決算書のない決算
成果をあげるための計画。倫理運動か、経済活動か。
2. 基本ルール(なすべきでないことと、なすべきこと)
基準の設定、適正な配置、そして評価。外部の目で組織を見る。
3. 成果を見るための意思決定
機会とリスク。反対意見の必要性。争いの解決。決定から行動へ。
4. 学校を責任あるものにするには(対話)
[Ⅳ部]人事と人間関係…職員、理事会、ボランティア、コミュニティー
1.人事
育成するには。チームをつくり上げる。仕事で人を活かすには。難しい決断。
後継者をどう選ぶか。
2.人間関係の鍵
双方向の関係。コミュニティーとの関係。
3.ボランティアから、無給のスタッフへ(対話)
4.理事会を機能させるには(対話)
[Ⅴ部]自己開発…人として、役員として、リーダーとして
1. あなたが責任者なのだ
2. 何をもって記憶されたいか
3. もう一つの経歴としての非営利機関(対話)
4. 非営利機関の女性役員(対話)
かつて私も「非営利組織の経営」に携わる者として、この本によって大いに啓発されました。アメリカの非営利組織の経営に関するマニュアルをいくつか翻訳したこともあります。しかし、公立学校でもこのような経営管理の手法が積極的に取り入れられるようになった、今の時点で振り返ってみて、NPOも結局は国家や行政、あるいは資本主義社会という大きな枠の中で動いているだけであるという、その限界を意識するようになりました。
かつて、第二次世界大戦中、日本のキリスト教会は自己の組織の存続のために国策との妥協、あるいは積極的な協力を余儀なくされました。たとえ崇高な「使命」を担っている団体であっても、体制内で自己の存続をはかる限り(それ以外にその団体が存在する場所はありません)、実際にはその範囲内での使命の達成ということしか許されていません。
非営利組織には、組織の社会的な影響力を強めるために地域の有力者を理事に加えるという傾向があります。しかしそのために組織の「政治的」行動範囲は自ら限定されてしまいます。社会的な有力者から構成される理事会が政治的には保守的な傾向を示すことは、ある意味で当然と言うものでしょう。
先に「脱して生きる」という項目で言及した「脱国民的中間社会」(労働組合、協同組合、市民団体、NPO・NGO、教会などの宗教団体)は可能性の問題であって、それらの組織も現実には体制内に存在しています。実際には(一部の政治団体、労働組合、市民団体、NGOなどを除いて)国家や行政、あるいは資本の領導に従う団体であることを免れていません。しかも国家はすべての結社を管理(あるいは監視)の対象とすることをねらっているように見えます(共謀罪の企図はそこにあるのではないでしょうか)。
だから「脱国民的中間社会」はネグリ・ハートの「マルチチュード」のようなものです。それは「常に―既に」と「いまだ―ない」との奇妙な二重性を帯びた時間を生きています。現実性と可能性とが交錯した空間に置かれていると言うべきかもしれません。
NPOは社会変革のエージェントとなる可能性を持っています。しかし同時に国策遂行の手段として自らの使命をそれに従わせる可能性も持っています。ドラッカーは「使命が第一」と言います。非営利組織のその使命はどこまで普遍的であるかが問われています。
「まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのものは、すべて添えて与えられるであろう」(マタイ6:33)。
人々は「なまえ」に惹かれます。有名であればそれだけで価値があるようにみなします。世に言うブランドがその一例です。銘柄はおのずからその品物が何の「なかま」(たとえば革製品)であるかを指示しています。そしてその銘柄の品物であれば、「なかみ」も保証されていると信じます。またそれを所有することで自分が満たされたと感じます。
自分が有名大学(「なまえ」のある大学)に入学し、その「なかま」に入れば、それだけで自分の「なかみ」も保証されたように感じ、誇らしさを覚えます。また有名大学に入学できるのであれば、どの学部に入るのかは二の次であるという人もいます。
商品を売り出すときには、どんな「なまえ」をつけるか(naming)が重要な意味を持ちます。会社や学校の「なまえ」も同様で、それはコーポレート・アイデンティティ(スクール・アイデンティティ)の不可欠の事柄とされています。「京浜女子大学」から「鎌倉女子大学」に名前が変わるなどということが起ります。「なまえ」が変われば、「なかみ」も変わったかのような印象を人々に与えます。
しかし一度「汚名」(ブランドのもう一つの意味)を着せられると、名誉挽回は至難のこととなります。かつての雪印乳業、今のホリエモンがその一例です。看板に偽りがあった、「なかみ」が違っていたとわかれば、評価は逆転します。
商品の「なまえ」はマーケットで浮沈します。売れ筋の商品名とその趣向は、直ぐに同業他社の追随するところとなります。そして企業は絶えず自社の商品のシェアの拡大(「なまえ」の浸透)をはかります。広報と営業に力を入れます。
なまえ・なかま・なかみは差別化の原理です。それは企業の戦略の一環です。どのように名づけるかということも重要ですが、その商品が何の「なかま」であるかを再定義することも、それに劣らず大切です。ビール瓶の製造工場は、ビールの「容器」を製造する会社です。コンセプトをビンから「容器」に変えるだけで、それはガラスだけでなく、缶やその他の材質を含むことになります。また中に入れるもののコンセプトをビールから「食品」(あるいはその他のもの)に変えるだけでも、そのガラスの容器にはジャムや漬物などのほかの食べ物、あるいは薬品その他を入れることが可能になります。大学が少子化の傾向の中で、伝統的学生のコンセプト(高卒で、18歳を過ぎた、20歳前後、あるいはそれに近い年令のフルタイムの学生)を「社会人」にまで拡大しつつあるのも、それと同様の事柄です。学びたい人であれば誰でも受け入れるということになります。
なまえ・なかま・なかみはマーケットの変動と共に変わっていきます。すべてが商品化された世界で、常住・不変のものは何もないかのようにさえ思われます。
しかしマーケットという、この「うたかた」の世界で、突如、「宗教心」は大切である、「愛国心」を持つべきであるという声が沸き上がってきました。そこに確固不動の立脚点があると言わんばかりです。「宗教心」や「愛国心」を持てば、自社の商品の売れ行きが増すということなのでしょうか。あるいはマーケットという仮の世界(売買ゲーム)の外側に、宗教的価値観を重んじ、国家を愛する本当の心の世界が存在すると言いたいのでしょうか。それがないから、フリーターや犯罪者が増えると言いたいのでしょうか。
片方で市場原理、競争原理を推進しつつ、もう片方で「敬神愛国」を説くのは一体何を意味しているのでしょうか。格差が拡大していると感じている人たち、競争に負けたと思っている人たち、あるいは競争から降りてしまった人たちに、「足るを知れ」、「分相応に生きよ」、「国のために犠牲になれ」と言っているとしか、私には思われません。
どうやらマーケットはマーケットだけで成り立っているのではなく、それは権力による支えを必要としているようです。新自由主義と国家主義の推進者は明治時代の開国の目標、すなわち「富国強兵」と、それを支えるイデオロギーである「欽定憲法」、「教育勅語」に舞い戻ろうとしているとしか考えられません。我々は「日本国」という「なまえ」のもとに、そしてその国体と国柄(誇らしき「銘柄」)のもとに存在しており、「日本国民」の一員(「なかま」)として、喜んでその責務を果たし、「忠君愛国」の「なかみ」を実現しなければならないと言われているのではないでしょうか。
「ねうち」はねぶみ、ねだんのことです。しかしここでは「そのものの価値」という意味で、値段から一応区別して使います。これもマーケティングの戦略の一つです。英語では3Psと言います。product, price, place のことで、プロダクトはもちろん「プロデュースされたもの」ですが、言い換えれば自分が売り出そうとしているものは何か、そのものの価値(ねうち)はどこにあるかを明確にすることを意味しています。プライスは文字通り価格設定(ねだん)のことです。プレースとは、そのもの(製品・商品)がどこで取引きされるかということで、要するにねらい(ターゲット)のことです。この戦略は非営利組織の経営にとっても重要であるとされています。
すべてが商品化されたこの社会では、社会運動家に対しても、ドラッカー流に、あなたは何を売り出そうとしているのか、それはどういう人々に対してどれだけの価値を持つのかと問いかけることは、ある意味で避けられないことであると言うべきでしょう。しかし社会運動家に対して、そのように問わなければならないということは、市場原理がこの社会にそこまで浸透してしまっているということでもあります。マーケティングの用語がそのようにコモン・ランゲージ(共通言語)となりつつあるということは、社会生活にどのような結果をもたらすのでしょうか。
市場原理の拡大、社会のあらゆる方面への浸透ということによって、何かが隠され、何かが失われつつあるのではないでしょうか。キリスト教が結婚式産業に組み込まれ、仏教が葬式産業の一翼を担い、マスコミが情報産業となり、学校が教育産業と化しつつある世界で、何かが隠蔽されてしまっているのではないでしょうか。ネグリ・ハートは非物質的労働が社会形成の原理となることによって、〈共〉(the common)の領域が拡大しつつあると言います。しかし私に見えているのは、市場圏の拡大であって、〈共〉の拡大ではありません。その傾向の中で隠蔽されているものとは一体何なのでしょうか。
それこそが「生権力の企図」であると言うべきかもしれません。明らかな政治的反動、クーデターまがいの体制変革が進行しているにも拘わらず、人々がなぜ立ち上がらないのかと言えば、人々の住む世界が市場圏に覆われてしまっていて、政治的デマゴギーを批判する言葉を失ってしまっているからではないでしょうか。あるいは自らの「生政治的領域」に接近する回路が断たれてしまっているからではないでしょうか。いわば生活が浮遊していて、地に足がついていないからではないでしょうか。
非営利組織の「使命」がマーケティングの文脈で語られ、営利組織のそれと区別できないものとなりつつある時代、哲学者も自分の思想を「売り物」にしなければならない時代に、市場圏の外に人々の連帯を築くことはいかにして可能となるのでしょうか。