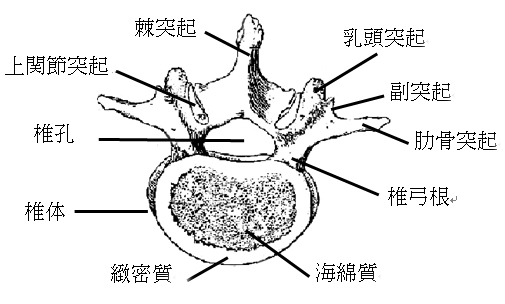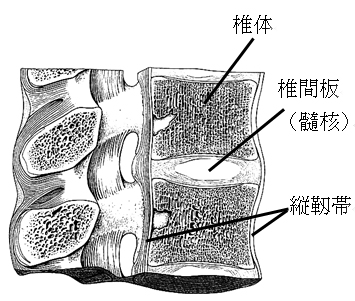以前は黄色い鼻水を垂らして遊びまわる子供をそこらじゅうに見ることが出来ました。黄色い鼻水は一般的に鼻の中の炎症物質が外に出ている状態です。しかし、最近は鼻水が外に排出されずに中に貯まってしまう子供が多く、「副鼻腔炎」(皆さんになじみのある病名では「蓄膿症」です。)にかかることがあるようです。
まずは、西洋医学的な見方からお話しましょう。鼻の周りの頬や額の骨の中には、副鼻腔と呼ばれる四つの空洞があって細い通路でつながっています。この副鼻腔の粘膜の炎症が副鼻腔炎です。副鼻腔炎には急性と慢性があって共通する症状は黄色い粘り気のある膿のような鼻汁です。子の鼻汁が副鼻腔の中にたまるので別名「蓄膿症」といわれます。
急性副鼻腔炎は殆どといっていいほど風邪に引き続いて起こります。熱が出たり、頭痛がしたりといったこともよくあります。初めはサラサラと水っぽい鼻水が出ますが、それがだんだん粘り気を帯びた鼻汁に変わってきて鼻を何回かんでも止まらなくなるか、詰まってしまって、出にくくなります。この状態で長引くと息苦しくなったり、おっぱいやミルクがうまく飲めなくなるので不機嫌になります。
慢性副鼻腔炎は風邪や扁桃炎をよく起こす子が急性副鼻腔炎を繰り返したり、急性副鼻腔炎をきちんと直しておかないと、慢性副鼻腔炎に移行します。慢性副鼻腔炎は黄色い鼻がいつも出ているか鼻が詰まっているので、頭が重く根気が続かなかったり、記憶力が低下したり、においを感じられなくなったりします。いつも鼻をすすっているので中耳炎も起こしやすくなります。
急性も慢性も治療法は一緒で、細菌を殺す抗生物質や、炎症を鎮める抗炎症剤を内服し、膿がたまっているときは注射針よりも太いはりを鼻の穴から副鼻腔にいれて、膿を吸い出します。その後、鼻の中を洗浄して、吸入器で薬を噴霧して直します。
続いて東洋医学の見方をお話しましょう。副鼻腔炎が風邪の後に発症しやすいということを先にお話しましたが、風邪は体が冷えたことによる反応です。その結果起こる副鼻腔炎も冷えによる現象なのです。冷えは不規則な生活時間で過ごしたり、飮食の不摂生によって起こります。その結果、鼻粘膜は分泌物を多く出します。これが「鼻水」です。この状態で更に冷えると粘膜は腫れて鼻づまりを起こします。状態が進むと身体は改善しようとして熱を持ち始め、鼻水は黄色く変化していきます。これが「膿」です。体が元に戻ろうとする力があれば、排膿しますが力がなければ膿がたまります。力がないというのは体が冷え切っていることを意味します。このように「副鼻腔炎」(蓄膿)を捉えるのです。だから治療も簡潔化していて、体が温まるように行なって、膿を出す力を付けてあげるのです。用いる道具は、小児はりですが、冷えが強ければお灸も用います。鼻の中に注射針を突っ込んで強制的に排膿すれば粘膜はそのたびに傷ついてしまいます。そのため、次第に自分で膿を出す力さえ失っていきます。慢性副鼻腔炎は急性期のときにそういった処置をした結果起きるのではないかと考えられないでしょうか?
鼻は呼吸器の最も外側にある器官です。鼻が弱れば肺も弱り、酸素の取り入れも不十分になります。喘息や気管支炎、更には身体全体の調子も悪くなりがちです。
小児はりで早期治療を行なって、お子さんの健康を維持してあげませんか?