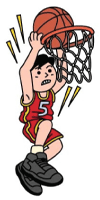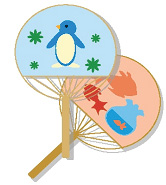平成15年3月21日、我々清野鍼灸整骨院では、中国の蘇州にある蘇州華佗鍼灸機器総合工場を見学してきました。その様子を簡単にご報告致します。
華陀という会社は現在、全世界で使われている鍼灸用鍼の56%を製造しており、輸出国も100ヶ国以上を数える世界規模の会社です。中国国内のみならず、豪・欧・米の品質保証許可である、CEマーク・TUV・ISO9002などを受けており、品質においても世界に認められています。今回訪れた蘇州の工場は、140年の歴史のある華陀で最も古い工場でした。
現在、鍼や灸の製造は郊外の工場へ主力を移してしまっているため、全工程を目にすることはできませんでしたが、中国鍼を手作業で製造する工程を初めてみることができました (中国鍼は鍼柄(手で持つところ)が針金を巻いて作ってあるものです) 。基本的に、鍼柄を巻きつける工程までは、以前見学した日本の鍼工場と同様で、医療用ステンレスの針金を切断し、鍼先を研磨するという工程です。この工場では針先の研磨を熟練した職人が手作業で行っていました。また、鍼柄を巻きつける作業は、これもまた一本、一本手作業で、作業台の上に設置してある電動ベルト(モーターにベルトを通してあるもの)を用いて驚くべきスピードで巻きつけていました。現在、郊外の工場ではこの巻きつける作業もオートメーション化されているそうですが、以前は全て手作業で作っていたかと考えると気の遠くなる思いがします。最近活気があると言われる中国のマンパワーを感じました。
現在この工場では、日本の販売会社から依頼されて、日本式の鍼の製造も行なっているそうです。工場長の話では、「鍼の素材・鍼先の質の点で、まだ日本の製品に敵わないところがあるが、徐々に改良していく予定です。そのために日本の工場と技術交流しています。」とのことでした。日本の販売会社はディスポーザブル鍼(使い捨て鍼)の、より低価格化を目指しているため、その労働力を中国に求めているのです。
中国で生まれた鍼治療が日本に渡り、日本で独自の発展を遂げたとともに、日本では質の高い道具作りが行なわれてきました。その技術が中国に戻り、品質が高く・安全性の高い道具作りが世界的にも行なわれるようになりました。
今回中国の工場を見学し、鍼灸治療の安全性が世界的に確立したことを確信しました。
今後も当院は、鍼灸治療の世界水準を提供できるよう努力してまいります。