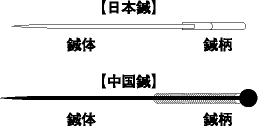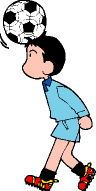|
沐浴は筋肉を弛緩させ、血液の循環を高め、皮膚を清潔にして新陳代謝を促進し、精神を安静にします。中国ではこの沐浴は、民族的にも宗教的にも行なわれていました。
元旦には「五香湯」を煎じて湯あみをすることが行なわれました。
この五香湯とは青木香を煮て作ることです。
その他に蘭香、荊芥、白檀、木香なども用いられました。
これらは神おろしの目的や、辟邪や頭痛の治療などのほか、疾病予防の働きもあったようで、蘭香の代わりに甘松も代用されました。
●上巳沐浴節
陰暦三月上旬の巳日に人々が近くの川に行き、洗濯したり、体を洗ったり、辟邪・祈福をしましたが、これを「祓禊(ばつけい)」といいました。
この風習は中国では周の時代からありました。
わが国では、神道でいう「みそぎ」や「斎戒沐浴」などもこの「祓禊」と同じ意味でしょう。
滝に打たれたり、河に入って身を清めたりするのは少し宗教的行事かもしれませんが、やはり養生という意味を考えてみる必要もあるようです。
●端午薬浴
五月五日は重要な沐浴日です。
中国前漢時代の「夢書」には、「蘭湯で湯あみをすればしらみなどが取り除かれ諸々の病気が癒る」としるされています。
この薬浴は現在の中国でも愛用され、たとえば、関節リウマチでは防風・艾葉・透骨車が、できものには青蒿・天泡草・艾葉などが実際に用いられていることを思えば、その歴史も古いと言わざるをえません。
わが国の端午の「菖蒲湯」も民族と疾病予防が結ばれた養生の一つのサンプルでもあります。
●洗毛虫毒(六月六日)
この頃夏至近くになると、暑さが増してきます。
中国湖南省の農村では、子供に沐浴させるだけでなく、「洗毛虫毒」といって、牛・犬・猫などの家畜を河で洗う行事があるといいます。
しらみ退治の目的で行なわれるそうです。
以上述べたところから更に追加すると、「黄帝内経素問」五蔵生成篇に「腎痺という下腹部に気がたまった病気には、清水で沐浴して寝るのがよい」とあることから、沐浴がすでに治療目的ですでに用いられていたことがわかります。
「千金月令」では「二月二日、枸杞湯で湯あみすれば人の顔はつやつやとして、不病不老となる」とあります。
枸杞は不老長寿のための代表的薬物でもあります。
沐浴について詳細をきわめ、それを儀式的に高めたのは、「雲笈七籖」(巻四十一、沐浴)でしょう。
道教の斎戒としての沐浴、その吉日、髪を洗うなど細かくしるされており、浴室は清らかで香わしくなくてはならず、便所、かまど、汚い土地、牢獄、死体安置所などの近くはよくないなどと書かれています。
たとえば、「立春の日の天気の良い朝、白?・桃皮・青木香の三つを煎じて沐浴するのは吉」「七月十一日枸杞湯を煎じて湯にいれ、沐浴すれば不老不病。
二十三日にすれば髪の毛は白くならず、二十五日にすれば長寿を保つ」としるされています。
最近はやりのアウトドアやオ−トキャンプは一種の沐浴なのでしょうか?
いずれにしてものんびり日光浴するのは養生の重要な一つのようですが、忙しい日本人には最高の贅沢のようですね。
メニューへ
|
![]()
![]()