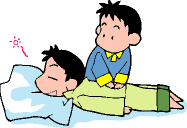![]()
![]()
![]() 清野鍼灸整骨院
院長 清野充典
清野鍼灸整骨院
院長 清野充典
健康研究サ−クル「オアシス」に御入会下さいましてありがとうございます。
私共は皆様の病気・外傷を改癒すべく、治療にあたらせていただいておりますが、古くより東洋医学では、「未病を治す」という言葉があります。
病気にならないようにするのが医学の務めとされております。
患者さんの健康の維持・増進の手助けをさせていただくのが医学の本道と考え、当会を発足することにしました。
皆様の健康管理の窓口として、是非当会を御利用下さい。
「清野鍼灸整骨院」は、昭和62年2月2日に最新の鍼灸治療を広く皆様に提供するため、京王線の調布駅南口にて開業致しました。
その後母校明治鍼灸大学の卒業生を中心に治療所を拡充、平成3年4月6日に東府中駅前に「明治鍼灸整骨院」開業し、地域住民の健康管理のお手伝いをさせていただいています。
尚、平成4年6月10日、清野鍼灸整骨院は調布東口に移転し、現在に至っています。